第1章 舟越保武作品との出会いの旅
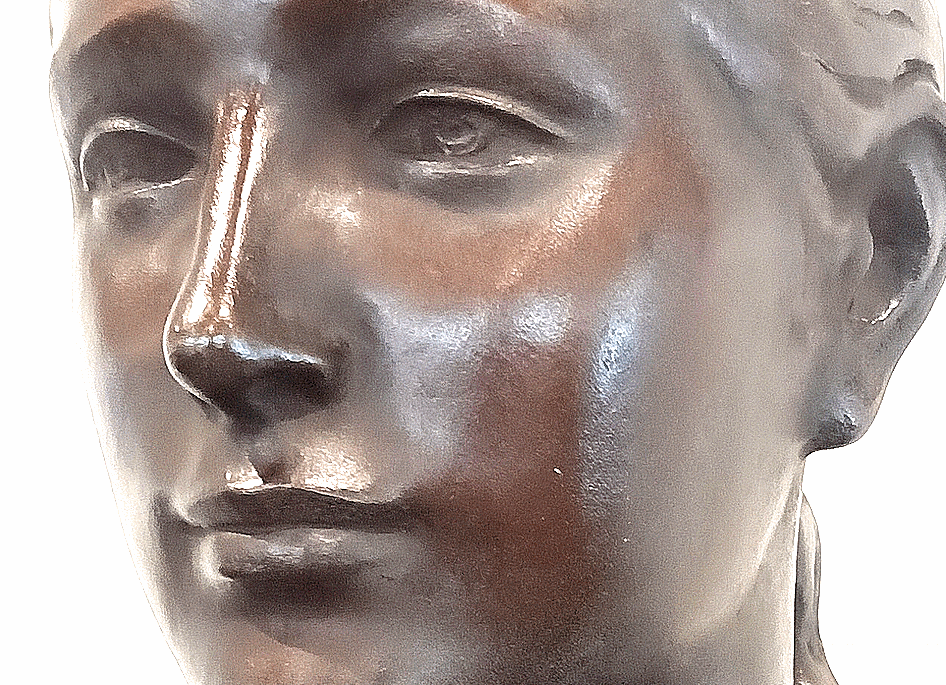
今から二十年以上前、私は舟越保武の作品に出会った。きっかけは、岩手県立美術館で松本竣介の《立てる像》が展示されていると聞いたことだった。
休日を利用して訪れたその日、私は竣介の絵の前に立ち尽くした。《立てる像》の人物は、未来をまっすぐに見据え、静かに自らの道を見定めようとしていた。その姿に、私は言葉では言い表せないほどの決意と孤独の美しさを感じた。
展示室を出ようとしたとき、ふと隣の部屋に目をやると、そこに彫刻作品の展示室があった。何気なく足を踏み入れたその瞬間、私は思いもよらぬ世界と出会うことになる。そこには、舟越保武の《ダミアン神父》があった。
なんという姿なのだろう。この方は――。粗く刻まれたブロンズの表面から、静かな炎のようなものが立ちのぼっていた。その瞬間、私の心は驚きに満たされ、身体が動かなくなった。「ダミアン神父」とはどんな人なのだろう。なぜ、船越はこのような姿を彫ったのか。問いが胸の奥で次々と生まれ、私はその場から離れられなかった。

その近くには、《原の城》という侍の像があった。口をわずかに開き、どこか遠くを見つめるその姿は、まるで亡霊のようだった。沈黙の中で何かを語りかけてくるような気配があり、私は背筋が凍るような感覚を覚えた。この二つの作品に出会ったとき、私の心は動揺と疑問でいっぱいになった。
ふと後ろを振り向くと、そこに若い女性の顔があった。その表情は驚くほど穏やかで、清らかだった。「なんと聖なる気配なのだろう」――私は思わず息をのんだ。《ダミアン神父》や《原の城》の激しい苦悩とは対照的に、その女性の顔には、祈りにも似た静けさと気品が宿っていた。私は言葉を失い、ただその前に立ち尽くした。
この彫刻家は何という人なのだろう。激しさと静けさ、苦悩と聖性――その両極をひとつの手で形にする、その心とはいかなるものなのか。私の「舟越保武の彫刻との旅」は、このとき、静かに始まった。