柳原義達における「守・破・離」──存在の祈りへ至る道
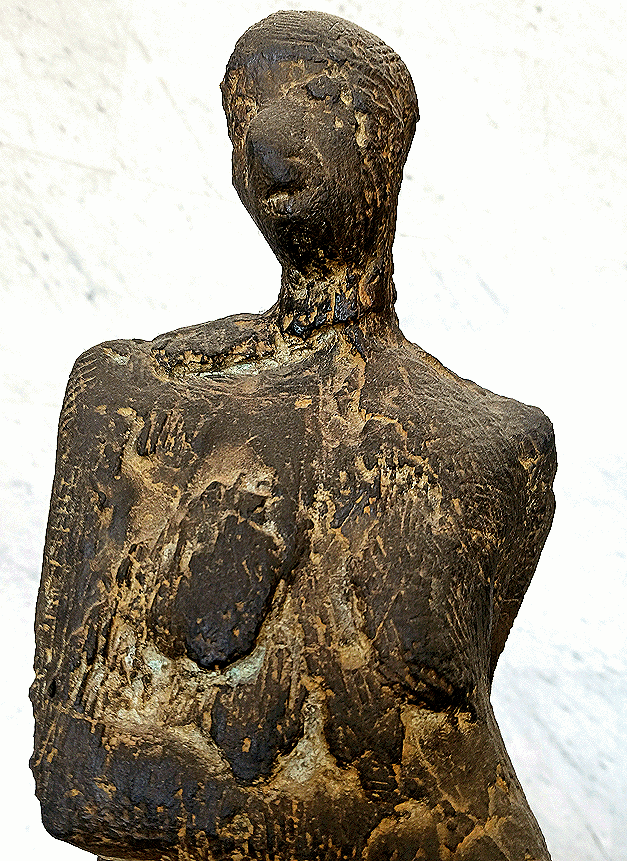
第1章 「守」から「破」への道
柳原義達は、新制作派協会の創立に参加しながら、ロダンやブルーデルなどフランス近代彫刻を手本に、具象的な人体彫刻を制作していた。当初は師の教えを忠実に学び、形と量感を正確に捉える「守」の段階にあったといえる。彼にとってそれは、いわば技と型を身につける修行の過程であり、武道や芸道における「守・破・離」の第一歩であった。
しかし、次第に柳原はその模倣の延長線上には、自らの彫刻の本質がないことを感じはじめる。42歳で渡仏し、パリでジャコメッティやブルーデルの影響を直接受けることで、彼の内面に大きな転機が訪れた。ロダン的な情熱でも、ブルーデル的な構築でもなく、「自分の中にしかない形」を掘り起こそうとする強い衝動が芽生える。ここから柳原は、型を破り、自らの表現を模索する「破」の段階へと歩み出す。

その「破」の精神が最初に形となって現れたのが、《黒人の女》や《赤毛の女》である。
これらの作品では、均整のとれた美しさは捨て去られ、荒々しい表面と歪んだ量感の中に「生きている者の苦しみ」や「存在の重さ」が刻まれている。
私は神戸で約25年間仕事をしていた関係で、偶然この二つの作品に出会った。ポートアイランドの商工会議所に設置されたその像を初めて見たとき、思わず「なんて気味が悪い作品なんだ」と感じたことを覚えている。しかし今になって思えば、その違和感こそ、柳原が従来の“美の形式”を壊し、人間の根源に触れようとした叫びであったのだ。
佐伯祐三がブラマンクに作品を見せ、「アカデミズム」と吐き捨てられ、「自分の絵はどこにあるのか」と叱咤されて独自の道を模索したように、柳原もまた自らの殻を破る覚悟を決めた。
実際、柳原はブラマンクに会っており、その影響は無視できない。彼にとって「破」は、師を超えるための反逆ではなく、自らの魂を見つめる孤独な旅の始まりであった。
やがて柳原は、《犬の唄》《道標》《風の中の鳥》といった作品群へと至る。そこでは、形態の完成よりも「祈り」そのものが彫られている。ジャコメッティの影響は明白だ。ジャコメッティは、人間の「存在する」ことの不安と孤独を極限まで削ぎ落とし、痩せ細った像の中に“存在の痕跡”を刻み続けた。
柳原もまた、完成を拒みながら、ただそこに“ある”という存在の真実に迫ろうとした。しかし、ジャコメッティの孤絶した人間像とは異なり、柳原の彫刻には自然と人間が溶け合う静かな祈りが宿っている。
それは「離」の境地──形を超えて生命の尊厳を表す段階である。
柳原にとって「離」とは、技巧の完成でも、思想の到達でもない。それは、形を離れ、沈黙の中に生命の声を聴くための、祈りの行為であった。《犬の唄》の静かな佇まい、《道標》の見上げる手の構えは、いずれも“生きることそのものが彫刻”であるという柳原の到達点を象徴している。
第二章 沈黙の祈り──《犬の唄》と《道標・鳩》にみる「離」の境地
柳原義達の晩年に至る彫刻は、声なき「祈り」を形にする試みであった。それは宗教的な祈りではなく、生きるという行為そのものを肯定する沈黙の姿勢である。その象徴的な作品が《犬の唄》(1961年)と《道標・鳩》(1974年)である。この二つの作品は、一見対照的でありながら、ともに「存在の尊厳」と「自然との共鳴」を静かに語りかける。
① 《犬の唄》──存在の叫びを内に秘めた沈黙
《犬の唄》は、吠える犬の姿を描いてはいない。口を閉じ、わずかに首を傾け、静かに立ち尽くすその姿は、異様な緊張感をもって空間に存在している。この犬は、声を発しないかわりに、その沈黙自体が唄であるかのようだ。
ロダンが『カレーの市民』で肉体の苦悩を外へと叫びとして表したのに対し、柳原はその叫びを内面へと沈潜させ、沈黙の中で「生きる痛み」を彫り出した。それは、外に向かう表現から内へと還る、「離」の境地を象徴している。
表面は荒く、ブロンズには指の痕跡がそのまま残されている。しかしその荒々しさは未完成ではなく、生命が呼吸する皮膚のような温度を持っている。
柳原は「完成した形ではなく、生きている形を求めた」と語っている。《犬の唄》の犬は、完成を拒む生であり、声を上げずとも存在そのものが唄となる。それは、彼が彫刻という行為のなかに見出した“祈りの原点”である。
② 《道標・鳩》──自然と存在の融和としての祈り
一方、《道標・鳩》は、「道標(みちしるべ)」の上に鳩が静かに佇む姿を捉えた作品である。人物像ではなく、鳥という最も自然な生命を通して「祈り」のかたちを掘り出している点に、この作品の独自性がある。
柳原が見つめたのは、擬人化されたドラマではない。鳩という小さな生命が、風や光の流れの中で静かに呼吸し、自然の力と響き合って存在している姿であった。その造形は、見る者に“生きることの静けさ”を思い出させるように、自然と共に在る生命のかたちをそっと示している。この静けさこそが柳原にとっての祈りであり、「自然と人間が溶け合う沈黙の中の孤独」を象徴している。
ここにはジャコメッティの影響も明確に見られる。ジャコメッティが“存在の孤絶”を極限の形態で表したのに対し、柳原は自然と共にある“存在の融和”を掘った。彼の鳩は、孤独に立つのではなく、風や光の中で呼吸している。この「風とともにある存在」という感覚が、柳原の彫刻を西欧的実存の孤独から解放している。
③ 沈黙の美学──叫びから祈りへ
ロダンが「動」と「激情」を通して人間の存在を表したとすれば、柳原は「静」と「沈黙」を通してそれを掘り下げた。彼は、叫ぶことによってではなく、沈黙することによって生命の深さを示そうとした。この沈黙は、感情の抑圧ではなく、外界と響き合うための内なる静けさである。
それは、表現の極限に到達した芸術家が辿り着く“無言の言葉”であり、その沈黙の中にこそ、形を超えた「祈り」と「生命の尊厳」が宿っている。
④ 「離」の精神──形を離れて生を彫る
柳原は、形の完成を目指すことを拒んだ。彼にとって彫刻とは、完成品を作る行為ではなく、生きることそのものであった。「彫刻という作品に、生きるという祈りを込めて形にしていった」――この言葉に、彼の芸術の核心が凝縮されている。
《犬の唄》に見られる内なる声なき唄、《道標・鳩》における空と風の中の静かな祈り。それらは、いずれも彼が「離」の段階で到達した世界観、すなわち
「沈黙の中にある生命の尊厳」を形にしたものである。
柳原義達の彫刻は、もはや人間を表すための“形”ではない。そこに在るのは、形を超えて生きる者たちの「存在の気配」そのものである。
この静かな気配こそ、柳原が人生をかけて彫り続けた「祈り」であり、「魂の証」であった。この「風とともにある存在」という感覚が、柳原の彫刻を西欧的実存の孤独から解放している。