柳原義達の晩年 ― 統合の彫刻としての「未来への希望と確信」
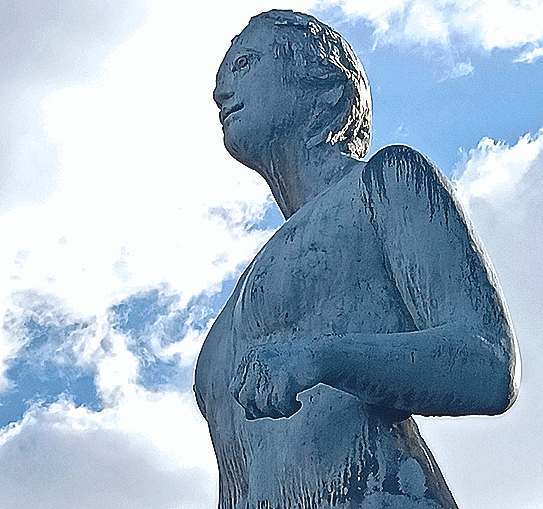
柳原義達の晩年の作品には、若き日の激しい格闘を越えた穏やかな確信が宿っている。そこには、長い時間をかけて彫り進められた人間存在の核心があり、生命への祈りが静かな光として形に結晶している。若き日の柳原は、形を通して生命を探る彫刻家であった。しかし晩年に至ると、形を超えて生命そのものを語る彫刻家へと変貌している。その変化こそが、柳原芸術の到達点、すなわち「離」の境地である。
エリクソンの心理発達段階論によれば、人間の成長の最終段階である老年期には、「統合性」と「絶望」という二つの方向性がある。自らの人生を受け入れ、過去の経験を統合して肯定できたとき、人は静かな平安に至る。それが「統合性」であり、柳原の晩年の作品にはまさにその精神が具現化している。彼の作品はもはや苦悩や孤独の象徴ではなく、人間の生のすべてを受け入れた上で、未来を信じる確信へと変わっている。
柳原は、東京美術学校でロダンやブールデルの系譜に学び、若いころは具象表現の中で「生きた形」を追い求めた。しかし彼にとって模倣は出発点に過ぎなかった。フランス留学でジャコメッティに出会い、「形を写すこと」ではなく「存在を刻むこと」へと視点を転じた。人間の外形を超え、その内奥にある「生命の呼吸」や「存在の震え」を捉えようとしたのである。この時期、彼は形式的な美から離れ、彫刻を「生きる行為」そのものとして捉えるようになった。それは、師の型を「守り」、それを「破り」、ついに自らの道を見出す「離」の精神に通じている。
この「離」の境地を象徴するのが、神戸ポートアイランドに設置された《犬の唄》(1981年)である。右手を前に差し出す人間像は、内面の祈りから外界への呼びかけへと転じ、未来を見据える姿となっている。かつての《道標・鳩》の人物が、見上げる祈りの姿勢で「内なる生命」を感じさせたのに対し、《犬の唄》は明らかに外に向かって開かれている。そこには、孤独の中にあっても未来を信じる強さ、そして「今を生きる人間」への深い共感が込められている。
銘板に刻まれた
今日の仕事をするために
昨日を反省し
明日の可能性を生きる
という言葉は、柳原の人生哲学そのものである。若き日の彼が追い求めた「形の完成」ではなく、「生きることそのものを形にする」という思想がここに明確に表れている。「明日の可能性を生きる」とは、未来を恐れず、過去を悔やまず、今を誠実に生きることへの誓いである。つまり、この作品は人間の成長の最終段階である「統合性の確立」の姿をそのまま形にしたものである。
柳原は、老いを「終わり」ではなく、「成熟した創造の時期」として受け止めた。彼にとって老年とは、身体の衰えや死への不安に直面する時期でありながら、同時に人生全体を俯瞰し、過去の苦難と向き合い、受け入れる時期でもあった。エリクソンのいう「統合性」は、まさに柳原が晩年に到達した心の平安と一致する。彼の彫刻は、人生の光と影をすべて抱え込みながら、それを一つの形にまとめ上げることで、存在の肯定を語っている。
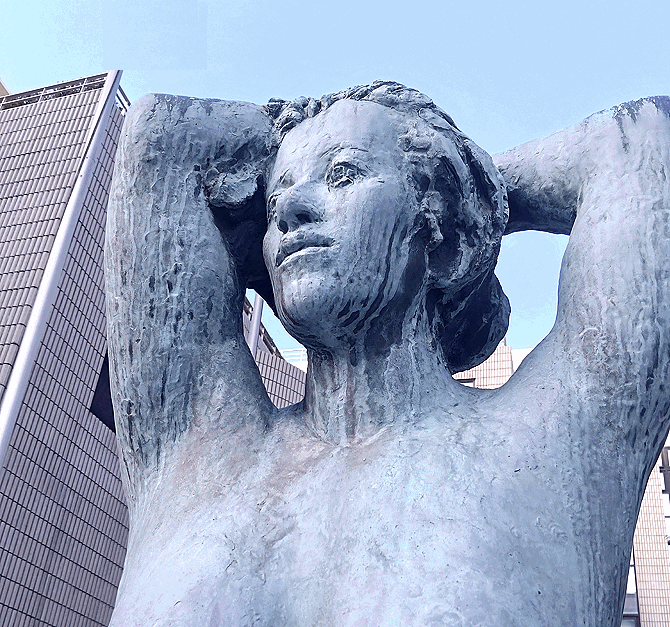
その到達点をさらに象徴的に示すのが、2000年に建立された神戸市東灘区の震災復興記念碑《すこやか》である。阪神・淡路大震災からの復興の記憶を刻むこの作品は、両手を頭上に掲げ、穏やかな顔で未来を見つめる人物像である。
かつて《風の中の鳥》で示された「内なる祈り」は、ここでは確信と祝福のかたちへと昇華している。両手を高く掲げたその姿は、苦難を越えた人間の希望を象徴し、見る者に静かな勇気を与える。そこに表れた表情は、悲しみではなく、受容と平穏の表情である。柳原はこの作品において、過去の痛みを抱えつつも、それを未来への糧に変える人間の力を形にしている。
《すこやか》の顔は実にすがすがしい。そこには、自己を受け入れた人間だけがもつ透明な静けさがある。死を恐れず、人生を肯定し、すべての出来事を「生きることの証」として抱きしめる心――それが柳原の晩年の境地である。彼の彫刻は、もはや他者に訴えかける表現ではなく、存在そのものの静かな宣言となっている。彼は「生きるとは何か」という問いを長年にわたって彫り続け、その答えを晩年の作品に託したのである。
柳原の晩年には、苦悩や孤独が溶解し、穏やかな確信へと変わっている。若き日の彼を支えた「反骨の精神」は、今や「受容の精神」へと昇華し、生命の流れそのものを肯定している。その静けさは決して消極的な平和ではなく、激しい葛藤をくぐり抜けた末に得た能動的な安らぎである。まさにエリクソンが言う「統合性」とは、柳原の晩年の作品において、造形として具現化した心理的成熟の姿なのである。
彼が生涯を通して求めた「沈黙の中の生命の尊厳」は、晩年に至って「沈黙の祈り」から「確信の光」へと転じた。彫刻という物質的な制約の中で、柳原は人間存在の最も精神的な部分――すなわち、希望・信頼・感謝――を表現することに成功している。その形は、もはや現世的な勝利や成功を語るものではなく、人生を丸ごと受け入れた者だけが発する「安らぎの光」である。
晩年の柳原義達は、自らの人生と作品を一つに統合した芸術家であった。彼の作品は、死に直面しながらも「生きる可能性」を信じる人間の姿を讃え、過去と未来を結ぶ橋となっている。《犬の唄》や《すこやか》に表された「未来への希望と確信」は、単なる個人の到達点ではなく、人間全体の成長の象徴である。
柳原はその生涯を通じて、「彫刻とは人間そのものの成長である」ことを体現した。彼の作品は、見る者に「明日の可能性を生きる勇気」を静かに手渡す、統合の monument なのである。