沈黙の中の生命 ― 柳原義達における「生命の尊厳」と反骨の造形

柳原義達の彫刻を貫く中心的な主題は、「生きていること」そのものへの深い敬意である。彼は、生命を賛美するために彫るのではなく、沈黙のなかにひそむ「生の痛みと誇り」を形にすることで、人間存在の真実を見つめ続けた。それは、華やかな美の造形とは異なり、祈りと抵抗のかたちとしての生命の尊厳を追求する行為であった。
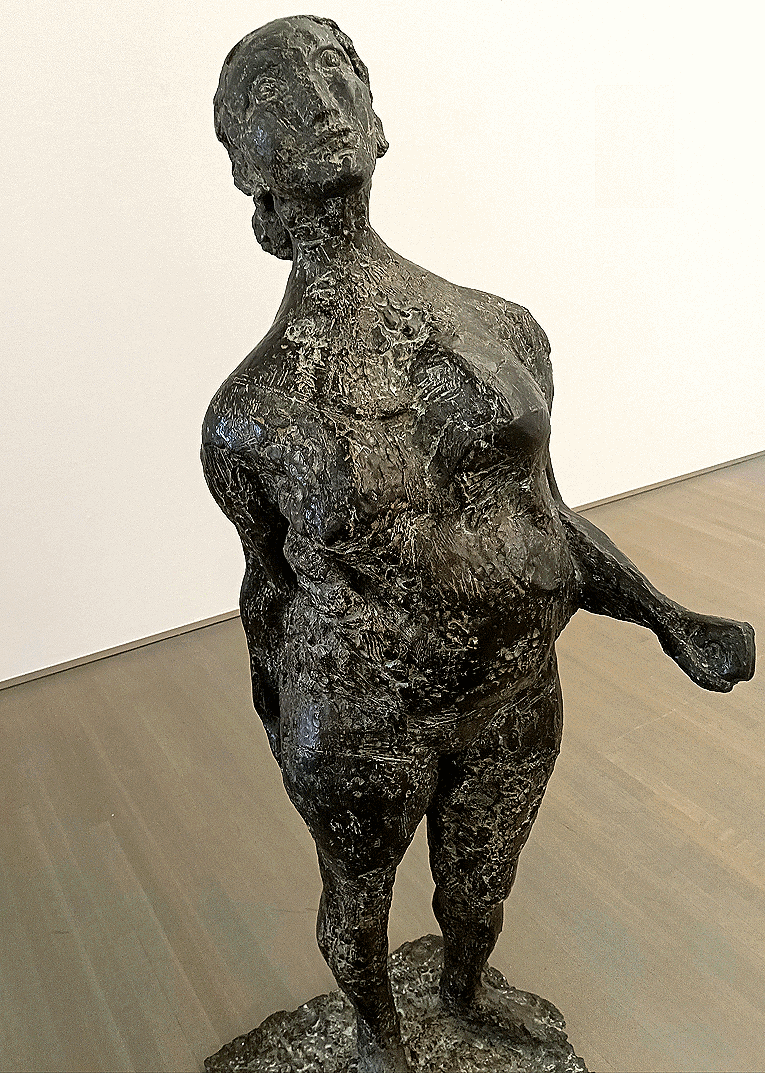
1. フランス体験と《犬の唄》の起点
柳原は1950年代にフランスに留学し、ロダンやジャコメッティらの作品に触れる。彼は、ロダンの肉体に宿る情熱、ジャコメッティの存在への透徹した凝視から強い衝撃を受けた。しかし同時に、これら西欧の彫刻が人間の「外へと向かう表現」であることを見抜く。
柳原はそれに対して、「内に沈む生命」を表す道を選んだ。ロダンが筋肉の動勢と感情を彫ったのに対し、柳原は「沈黙の中に宿る存在の意志」を彫ろうとしたのである。
この思想がもっとも鮮明に結実したのが、《犬の唄》(1961)である。題名に「犬」とあるが、その姿は明らかに人間的である。片腕を前に出し、もう一方を背に回す非対称の構えは、外に向けた従順さと、内に秘めた反抗を同時に刻んでいる。そこには、声を上げずに抗う存在の誇りが宿る。柳原は、怒りや激情を叫ぶのではなく、沈黙の姿にこそ人間の真の強さを見いだした。
2. 《犬の唄》とフランスの歌 ― 「沈黙の抵抗」の起源
《犬の唄》の題名には、柳原がフランスで出会った一つの歌が深く関わっている。十九世紀末の歌手エンマ・ヴァラドン(Emma Valladon, 1837–1913)が歌ったシャンソン《犬の唄(La Chanson du Chien)》である。この歌は、普仏戦争(1870–71)に敗れたフランス人の複雑な心情をうたったもので、外見上は征服者プロイセンに従順であらねばならないが、心の奥では誇りと抵抗を失わない――そんな沈黙の反抗を描いている。
柳原はこの歌を単なる哀歌としてではなく、屈服の仮面の下にある人間の意志の表現として受け取った。敗戦後の日本で生きる自身の経験とも重なり、彼は“声にならない誇り”というテーマに深く共感した。《犬の唄》はまさにこの精神を造形化したものであり、外的には従順な姿を保ちながら、内奥では強く燃える抵抗の意志を秘めた人間像である。
同時に柳原は、画家エドガー・ドガが描いたヴァラドンの肖像にも着目した。ドガの作品に描かれるヴァラドンは、背をそらし、両手を前に差し出す姿勢をとる。その優雅なポーズの中に、内に秘めた誇りと緊張が見える。
柳原の《犬の唄》の構え――一方の手を前に、もう一方を背に回す――は、このドガ的ポーズに呼応しつつも、それを静かな反骨の構えに変えている。ドガが舞台の優美を描いたのに対し、柳原は沈黙する人間の精神を刻んだのである。
3. ロダンを超える ― 模倣ではない独自性
しばしば柳原は「ロダンの影響を受けた日本の彫刻家」と評される。しかしその理解は表層的である。柳原はロダンの模倣者ではなく、むしろその先へ進んだ。ロダンの彫刻が「心の動きを外へ表す芸術」だとすれば、柳原の彫刻は「心の沈黙を内に保つ芸術」である。ロダンが肉体を通じて情念を叫ぶとき、柳原は沈黙の身体に「語らぬ意志」を宿す。そこには、西欧的な自己主張ではなく、声を出さずに世界と向き合う東洋的な精神がある。
柳原は、フランスの近代美術から多くを学びながらも、「形の完成」よりも「形が生きていること」を重んじた。彼の彫刻は、仕上げられた完結した像ではなく、生成の途中にある生命の痕跡として立ち現れる。彼は、形の完成を目指すのではなく、彫るという行為そのものに“生きるという祈り”をこめ、その祈りを形としてこの世に留めようとした。
この言葉は柳原の制作哲学の核心をなす。「祈り」は宗教的儀礼ではなく、生きていることへの畏敬と感謝のかたちであり、彫ることそのものが「祈ること」と同義であった。彼にとって作品とは完成品ではなく、祈りの痕跡=生の証であった。
4. 「沈黙による反骨」――声なき抵抗の造形
柳原の作品には、声を上げて抗う姿は一つもない。しかし、その沈黙は決して従順ではない。《犬の唄》の構えに象徴されるように、彼の彫刻には常に沈黙による反骨がある。
片腕を前に出し、もう一方を背に回す身体のねじれは、「外への服従」と「内なる反発」が同居する緊張を生む。柳原はこの緊張を通して、人間が外界に支配されながらも、内側で自らを守り、誇りを保つ姿を刻んだ。それは政治的な抵抗ではなく、存在の抵抗である。語らぬことで語る、沈黙の美学。その静けさこそが、柳原の反骨精神であった。
5. 「生命の尊厳」の具体的意味
柳原の言う「生命の尊厳」は、抽象的な理想ではない。それは、弱さを抱えながらもなお生きる姿勢そのものを指している。
戦争と敗戦を経験した柳原にとって、生命とは勝利や成功の象徴ではなく、傷を負いながらも生き延びることの重みだった。彼は「強さの美」ではなく、「生き続けることの美」を求めた。それゆえ、彼の作品には常にわずかな不安定さ、歪み、沈黙がある。それが「生きていることの証」であり、尊厳のしるしなのである。《道標・鳩》《風の中の鳥》においても、彼は飛び立つ瞬間ではなく、飛び立つ前の緊張を描いた。風に抗いながら立つ姿、静止した鳩の構えには、生命が内側から呼吸するような気配がある。柳原は、その「在ることの呼吸」を彫ろうとしたのである。
6. 結語 ― 祈りとしての彫刻
柳原義達の彫刻は、形の完成を目的としたものではない。彼は、彫るという行為そのものに「生きるという祈り」を見いだし、その祈りを形として刻み続けた。それは、生命への畏敬であり、人間が生きることをやめないための、静かな祈念であった。
沈黙の中にある生命の尊厳とは、声を上げずとも確かに生きている存在の深さであり、言葉を超えて世界と向き合う人間の姿である。柳原は、ロダン的な情熱を超え、沈黙をもって人間の誇りを語る彫刻家であった。彼の作品は、祈るように彫られた生命の記録であり、沈黙の中に燃える反骨の美学そのものである。