第3章 舟越桂の根底にあるもの―最低限の謙仰
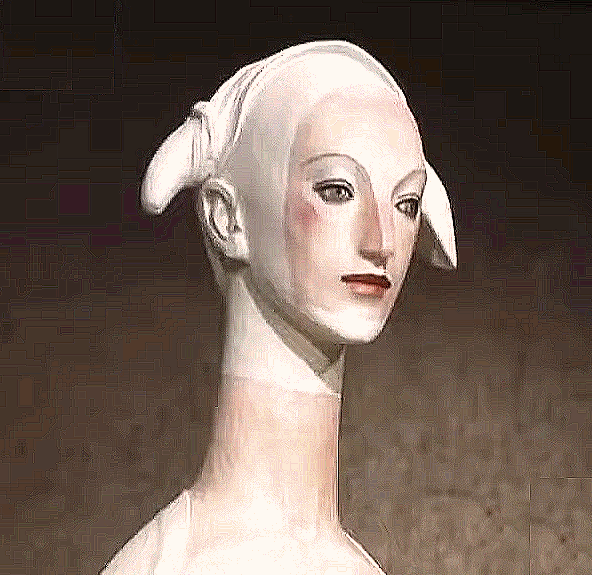
舟越桂の彫刻を理解するために、技法や様式、あるいは個別作品の主題から入ることは、必ずしも本質的ではない。むしろ彼の作品群が一貫して示しているのは、「彫刻とは何か」「人間はいかなる立場で世界と向き合うのか」という、きわめて根源的な問いである。本稿では、これまでの議論を踏まえ、その根底にある態度を「最低限の謙仰」という言葉で捉え直したい。
1 「彫る」とは何を意味しているのか
近代以降、彫刻は「作家が対象を観察し、構成し、完成させるもの」として理解されてきた。そこでは、作者の意図や造形力が前面に出る。一方、舟越桂の制作態度は、その前提を静かに裏切る。彼は一貫して、「何かを作ろう」として彫っているのではない。
木と向き合い、ノミを入れる行為は、そこに「すでに在るもの」を確かめる過程である。これは、棟方志功が語った「仏様が見えるから彫る」という言葉と深く共振する。対象は人間の側で構想されるのではなく、素材の内側、あるいは世界の側から立ち現れてくる。
この態度において、彫刻家は創造主ではない。あくまで、現れつつあるものに手を貸す存在である。
2 日本の木彫と宗教的態度
このような思考は、日本の木彫の伝統、とりわけ仏教彫刻と無縁ではない。日本において「彫る」という行為は、単なる造形ではなく、「仏を彫る」ことと深く結びついてきた。
重要なのは、ここで言う仏が、必ずしも特定の信仰対象に限定されないという点である。木の内部に「何かがある」と信じ、それを暴力的に作り出すのではなく、必要最小限の介入によって顕現させる。この姿勢こそ、日本文化の深層にある宗教的態度であり、謙抑と呼ぶべき精神である。
舟越桂は、特定の宗教を語らない。しかし、その制作態度は、きわめて宗教的である。それは信仰の表明ではなく、世界の前で身を低く保つ姿勢そのものだからだ。
3 ヨーロッパ近代との対照
私が指摘した、「彫るとは何かを作ることではない」という理解は、ヨーロッパにおいても中世キリスト教文化の中には存在していた。神の似姿としての人間像は、すでに在る秩序の写像であり、彫刻家はそれを読み取る存在だった。
しかし近代以降、科学的観察と客観性が支配的になるにつれ、この態度は次第に失われていく。彫刻は人間の能力と意志を示す場となり、世界は操作可能な対象へと変質した。
その文脈において、舟越桂の彫刻は、ヨーロッパが置き去りにしてきた態度を、外部から静かに突きつけたと見ることができる。彼の作品が国際的に強く受け止められた理由は、技巧の新しさではない。人間中心主義の先にある空白を、無言で示した点にある。
4 最低限の謙仰とは何か
ここで言う「最低限の謙仰」とは、自己否定でも謙遜でもない。それは、人間が世界の主人ではないという認識を、制作の前提として引き受ける態度である。
舟越桂の彫刻において、人間の姿は中心に置かれている。しかしそれは、支配者としての人間ではない。自然、時間、死、生と同じ地平に立つ存在としての人間である。だからこそ、彼の像は語りかけない。鑑賞者を説得しない。ただ、同じ場に在り続ける。
この態度は、宗教を超えた宗教性であり、普遍的な人間の倫理でもある。アインシュタインが語った「宗教的感情」と同様、それは特定の教義ではなく、世界の不可解さと秩序への畏敬から生まれる。
5 「同座」という鑑賞体験
舟越桂の作品が鑑賞者に強いるのは、理解でも共感でもない。「同座」である。鑑賞者は、像と向き合いながら、意味を読み取ることを一度諦めざるを得ない。そのとき初めて、時間が生じ、沈黙が生じる。
この沈黙の中で、鑑賞者は自分自身に問い返される。「あなたはいま、何を引き受けて生きているのか」と。その内なる会話こそが、美の経験であり、舟越桂の彫刻が担う役割である。
まとめ
舟越桂の彫刻の根底にあるのは、卓越した技術でも、強いメッセージでもない。それは、世界の前で身を低く保ち、なお人間を信じるという、きわめて静かな決意である。
「最低限の謙仰」とは、何も語らず、何も誇示せず、それでも彫り続ける態度のことである。舟越桂の作品は、その態度が形となった稀有な例であり、同時に、現代において失われつつある人間の立ち位置を、私たちに思い出させる。
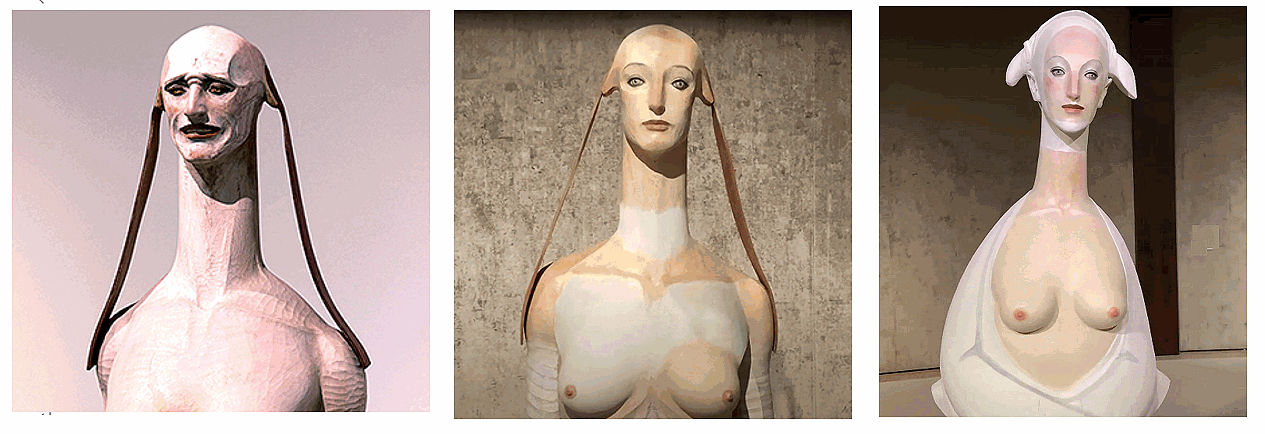
この意味で、舟越桂を理解することは、ひとりの彫刻家を理解することではない。人間が世界とどう向き合うべきか、その根底を問い直すことに他ならない。
補論 アインシュタインのいう「宗教的感情」とは何か
アルベルト・アインシュタインは、自らを無神論者とも宗教者とも定義しなかった。彼は繰り返し、「私は特定の宗教を信じないが、宗教的感情は深く信じている」と語っている。ここで言う「宗教的感情」とは、神や教義への信仰ではない。
アインシュタインが指していたのは、人間の理性や意志を超えた秩序が、この世界には確かに存在しているという感覚である。自然界の法則の精緻さ、宇宙の構造の必然性、それらが人間の理解を超えてなお一貫しているという事実に対して抱く、畏敬と驚嘆。その感情こそが、彼の言う宗教性であった。
彼はこうも述べている。「理論化できないものに対して、われわれは沈黙と敬意をもって向き合うしかない」。ここには、世界を完全に把握し、支配できるという近代的な人間観への明確な距離がある。
重要なのは、アインシュタインにとって宗教的感情とは、何かを説明するためのものではなく、むしろ説明し尽くせないものを前にしたときの態度であったという点である。それは信仰の対象を設定する行為ではなく、世界の不可解さを不可解なまま引き受ける姿勢である。
この意味で、彼の宗教的感情は「最低限の謙仰」と本質的に重なっている。人間の理性の限界を認め、なお世界に意味や秩序があることを否定しない。その二つを同時に引き受ける態度である。
舟越桂の彫刻が示しているのも、まさにこの地点である。彼の作品は、世界の意味を説明しない。祈りを形象化しながら、信仰を主張しない。ただ、人間が世界の前に立つときに必要な最小限の姿勢―傲慢にならず、虚無にも陥らない立ち位置―を、沈黙のかたちで示している。
アインシュタインの宗教的感情と、舟越桂の彫刻に通底するものは、特定の宗教ではない。それは、人間が世界と向き合うときに不可避となる、普遍的な倫理的態度であり、創造行為における根源的な緊張感である。
この意味で、舟越桂の作品が現代において深く響くのは、彼が宗教的主題を扱ったからではない。人間が世界を完全には理解できないという事実を、否定も回避もせず、造形の前提として引き受けたからである。
それこそが、アインシュタインの言う宗教的感情が、芸術の領域で静かに具現化した姿だと言えるだろう。
2026年1月15日
テキスト例