第5章 舟越保武の《ゴルゴダ》 ― 左手による祈りの造形 ―

第4章で述べた「聖女像」や「LOLA」の清澄な祈りの形は、やがて舟越保武自身の人生そのものと重なっていく。彼の最晩年の代表作「ゴルゴダ」は、もはや「彫刻をつくる」という行為を超えて、「生きること」「祈ること」そのものとなった作品である。
磔刑に処され、十字架から降ろされたイエスを抱く聖母マリア――。この主題は、ミケランジェロが晩年に取り組んだ「ロンダニーニのピエタ」を想起させる。ミケランジェロは視力を失いながらも、手探りでノミを振るい続けたと伝えられる。私はこの作品を写真でしか見たことがないが、そこに映るのは未完であるがゆえに、かえって完成を超えた「魂の形」であるように思う。視力を失った彫刻家にとって、その行為はもはや“造形”ではなく、“祈り”であった。肉体の限界を超えた場所に、魂の美しさが立ち上がっている。
舟越保武もまた、ミケランジェロに重なる人生を歩んだ。1987年、75歳のときに脳梗塞で倒れ、利き腕である右手が動かなくなった。彫刻家にとって致命的な出来事である。しかし彼は創作をやめなかった。わずかに動く左手で粘土を握り、格闘するように制作を再開したのである。その結果として生まれたのが、1989年、77歳のときに完成した「ゴルゴダ」である。この作品は、彼の生涯の集大成であり、肉体と精神の極限から生まれた祈りの彫刻である。
NHKの記録番組「老友へ〜83歳 彫刻家ふたり〜」で見た、舟越の姿が忘れられない。車いすに身を縛り、左手で粘土に挑むその表情は、何かに憑かれたようであった。それは闘いであり、祈りでもあった。舟越は自らの運命と、神と、そして自分の存在そのものと戦っていたように見える。彫刻刀を持つことも困難な身体で、なお形を刻もうとする姿に、私は人間の底知れぬ力を見た。
「ゴルゴダ」とは、イエス・キリストが磔刑に処された丘の名である。この地名を聞くと、私はマルコによる福音書15章34節の言葉を思い出す。「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ(わが神、わが神、どうして私を見捨てられたのですか)」。この叫びは、人間イエスの苦痛の極限における孤独を象徴している。
舟越が右手を失ったとき、彼もまた創造者としての“死”を宣告されたに等しかっただろう。しかし、命は奪われなかった。その与えられた命をどう生かすか――その問いに、舟越は全身で応えたのだ。
彼は、動かぬ右手を嘆くことなく、残された左手でイエスを彫り始めた。それは、自らの運命と和解し、魂の奥底から生まれる「祈りのかたち」を刻む行為であったに違いない。
私は思う。舟越が彫ろうとしたのは、もはや外形としてのキリストではなく、彼自身の中に宿る“イエス”そのものではなかったか。彼の脳裏には、すでに明確なイメージが浮かんでいたのだろう。左手で粘土を切り刻み、掴み、押し出す――その一挙手一投足は、祈りであり、告白であり、魂の記録であった。
そして今、私は舟越が倒れたときとほぼ同じ年齢にある。「ゴルゴダ」を前にすると、単に一人の彫刻家の努力や執念としてではなく、「生きるとは何か」という根源的な問いを突きつけられる。身体の衰えや不自由さを超えて、なお創造し続ける人間の姿に、私は“信仰とは生きることそのもの”であることを学ぶ。舟越の《ゴルゴダ》は、痛みを抱えながらも、なお祈り続ける人間の尊厳を形にした作品である。
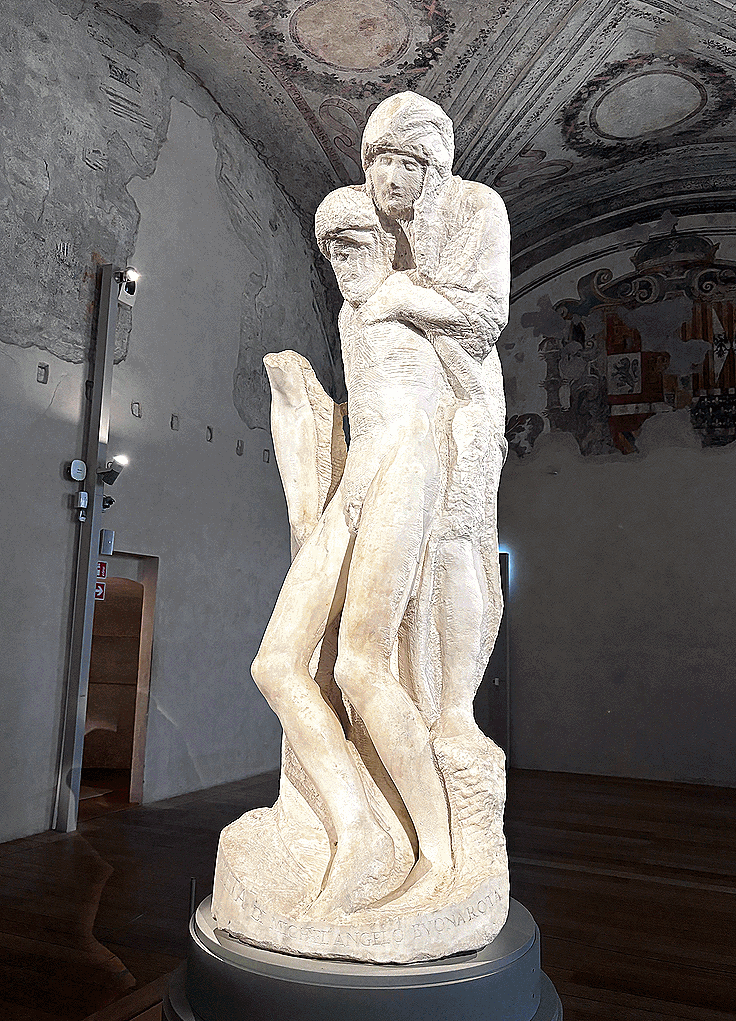
ミケランジェロ「ロンダニーニのピエタ」
この「ロンダニーニのピエタ」が未完のまま神へ捧げられたように、舟越の「ゴルゴダ」もまた、肉体の限界を超えた「完成された未完」である。そこには、形よりも大切なもの――魂の軌跡が刻まれている。左手による「ゴルゴダ」は、舟越が人間として到達した最も深い祈りの姿であり、彼の全生涯が凝縮された“終章”なのである。