第4章 舟越保武の聖女像 ― 祈りのかたちをめぐって ―
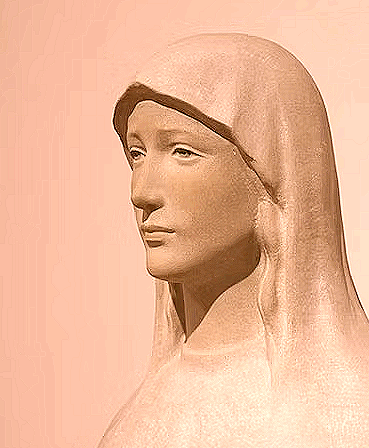
「原の城」で信仰の痛みと祈りの極限に触れた私にとって、舟越保武の作品群の中で「聖女像」と出会ったことは、まさに心の深奥に響く体験であった。
それは二十年以上も前、盛岡県立美術館を訪れた際のことである。展示室には「ダミアン神父像」や「原の城」をはじめとする宗教的テーマの作品が並び、静寂の中に祈りの気配が満ちていた。
その中で、ひときわ異なる静けさを放っていたのが、顔だけを象った小さな「聖女像」だった。沈黙そのものが形を得たようなその像は、柔らかな光を受けて、悲しみと安らぎとを同時に湛えていた。
私はその像の前で足を止め、長く動くことができなかった。その表情の中に、自分の心の奥に潜む痛みや祈りが映し出されているように思えたからである。言葉では言い尽くせない何か――人が苦難の中にあってなお美と信仰を求める力――それがこの小さな顔に宿っていた。私は思わず心の中で手を合わせていた。
舟越の作品は、信仰を示すための像ではなく、見る者の内にある「祈りの原型」を呼び覚ますものである。その清らかさは単なる美しさを超え、“聖なるもの”の静かな現れであった。
この出会いは、私の心に深く沈み込み、長い年月を経ても消えることはなかった。そして十年ほど後、思いもよらぬ再会が訪れる。当時、勤務していた職場の近くにあった神戸市役所の本庁舎。その一階ロビーを通りかかった際、まず目に留まったのはロダンの「青銅時代」だった。その奥に、ふとあの“祈りの気配”を感じた。近づいてみると、それは舟越保武の聖母像「LOLA」であった。
私は息をのんだ。十年以上の歳月を隔てて、再び舟越の聖女の顔と向き合ったのである。「LOLA」もまた顔だけを象った作品であり、しかし盛岡で見た「聖女像」とは異なる光を放っていた。そこにはもはや悲しみはなく、静かな微笑が浮かんでいた。柔らかく、しかし確固としたまなざしが、前を見つめている。私はその微笑みに導かれるように、気づけば同じように微笑み返していた。
芸術作品とは、見る者の心によって姿を変えるものだと、その時あらためて感じた。かつて震災を経て沈んでいた私の心には、「ダミアン神父像」の苦悩が重なって見えた。だが「LOLA」を前にした私は、そこに希望の光を見ていた。同じ作家の手による作品でも、見る者の心の変化によって祈りのかたちは変わる。その揺らぎこそが、芸術が生き続ける証であり、人が生きるということの深みを教えてくれる。

最近、舟越の聖母像を見ていると、私は奈良・興福寺の「阿修羅像」を思い浮かべることがある。両者の表情には、人間の複雑な感情が層をなして宿っている。奈良大学の文化財研究室では、マイクロソフト社の協力により「阿修羅像」の表情をAIで解析し、「怒り」「軽蔑」「嫌悪」「恐怖」「幸福」「中立」「悲しみ」「驚き」という八つの感情を識別したという。
この研究を率いた関根俊一教授は、「彫刻家がどのような人間の表情をモデルとしたのかを明らかにしたかった」と述べている。宗教彫刻の表情をAIが客観的に読み解く時代に、芸術は新たな段階へと進みつつあるのかもしれない。
だが、舟越の聖母像の前に立つと、私はそのような分析の向こうにあるものを感じる。作品が放つ「祈り」は、数値やデータで測ることはできない。その像と向き合う私の心が、日によって揺れ、ある時は光を感じ、ある時は沈黙に包まれる――その変化こそが、生きるということそのものなのだ。
舟越の彫刻は、信仰の表現であると同時に、「生きることそのものを祈りに変える」試みであった。彼の作品は、形の完成を目指すのではなく、魂の動きを刻むことで、存在そのものの尊厳を浮かび上がらせている。
「聖女像」から「LOLA」へ――そこには、苦難を超えて「赦し」に至る祈りの変遷が見て取れる。そして、その祈りの形の背後には、舟越自身の肉体的な試練が迫っていた。右手の麻痺という極限の状況の中で、左手だけで制作を続けた晩年の彼の姿は、祈りと創造が一体となった生の証であった。次章では、その「左手の彫刻家」としての舟越の最後の制作と、そこに宿る“魂の力”について考察したい。