同座するかたち ― 朝倉響子の彫刻

朝倉響子の彫刻作品を前にすると、不思議な安堵感が生まれる。理解しなければならないという緊張も、感情を動かされる圧迫感もない。ただ、そこに居合わせているような感覚が残る。多くの彫刻作品が、鑑賞者に意味や思想、感情を提示し、ときに心を重くさせるのとは対照的である。
この「気持ちよさ」は偶然ではない。朝倉響子は、彫刻という表現が本質的に抱えてきた「語りすぎる危険性」と、きわめて自覚的に向き合った作家である。彼女の信念は、彫刻を通して何かを主張することではなく、「彫刻が人とどのような関係を結ぶか」という一点に置かれている。
1.未決定性という造形原理
朝倉響子の作品に共通する最大の特徴は、「決めない」造形である。身体は歩き出さず、立ち上がらず、完全に休息することもない。姿勢は常に行為の直前、あるいは途中に留まり、完結しない。これは未完成ではなく、未決定性という明確な造形原理である。
とりわけ象徴的なのが、脚部、なかでもかかとの扱いである。多くの作品において、かかとは極端に持ち上げられ、重心は不安定なまま保たれている。かかとは人体において、動くか留まるかを決定する「身体の決断点」である。朝倉はその決断を下させない。行為の可能性を残しながら、決断を先送りする身体を造形することで、彫刻を時間の流れの中に留めている。この未決定性は、彫刻を静止した物体ではなく、時間を含んだ存在として成立させるための方法である。
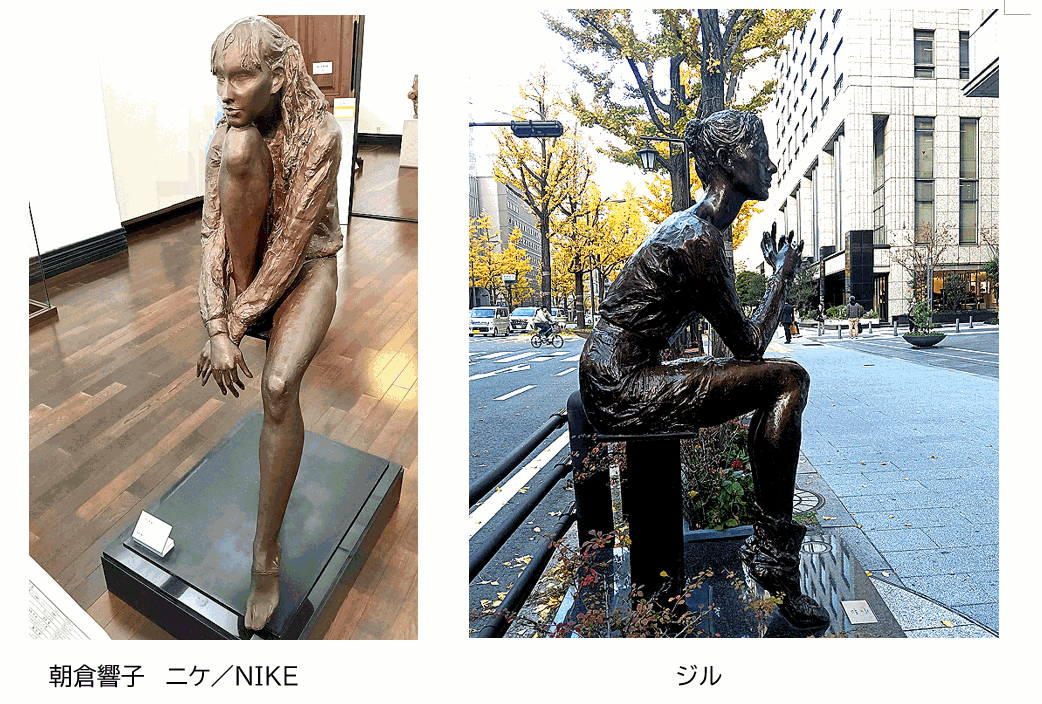
2.日常性の造形化
朝倉響子の彫刻は、日常の場面を描写しない。労働や会話、生活行為といった具体的な日常は示されない。しかし彼女が捉えているのは、日常が途切れずに続いている、その「間(あいだ)」の時間である。
日常とは、劇的な出来事の連続ではない。迷い、立ち止まり、何も起こらない時間が大半を占めている。朝倉の未決定性は、この日常の時間構造と深く一致している。だからこそ、彼女の彫刻は特別な出来事としてではなく、日常の延長としてそこに在る。
彫刻は本来、完成・永続・象徴を前提とする表現であり、日常性とは相性が悪い。その困難を承知のうえで、日常を壊さずに造形として成立させること。それが朝倉響子の挑戦であった。
3.鑑賞者への配慮としての倫理
朝倉響子の彫刻が鑑賞者にとって「気持ちがいい」のは、鑑賞者に何も要求しないからである。理解を迫らず、感情を指定せず、意味を押し付けない。多くの彫刻は、鑑賞者に対して「正しく向き合うこと」を暗黙に求める。そこに緊張や重さが生まれる。一方、朝倉の作品は「わからないままでいられる」ことを許容する。これは、鑑賞者の内面に介入しないという、きわめて高度な倫理である。都市空間に置かれた彫刻にとって、この態度は決定的に重要である。都市は日常の場であり、美術のために立ち止まる場所ではない。朝倉の彫刻は、都市の流れを遮らず、空間を占拠しない。そこにあるが、支配しない。この控えめな姿勢こそ、都市彫刻としての成熟である。
4.「同座」という思想
日本思想には「対座」と「同座」という考え方がある。対座とは、主体と客体が向き合い、意味や教えが伝達される関係である。一方、同座とは、区別を超えて同じ場と時間を共有する関係を指す。
美術史的に見れば、多くの彫刻は「対座」を前提としてきた。像は語り、鑑賞者は受け取る。そこに緊張と重さが生じる。しかし朝倉響子の彫刻は、明確に「同座」の位置に立つ。像は鑑賞者に向かって立たない。見上げさせず、意味を示さず、感情を導かない。その結果、鑑賞者は像と向き合うのではなく、像と同じ場所に居ることになる。
未決定性は、この同座を成立させるための造形条件である。決めない身体は、鑑賞者の上にも前にも立たない。彫刻は教える存在ではなく、ただ同席する存在となる。
5.父・朝倉文夫との比較 ― 写実から同座へ
朝倉響子を論じる際、父・朝倉文夫の存在は不可避である。朝倉文夫は、日本近代彫刻を代表する写実主義者であり、人体を厳密に観察し、構造として把握することを彫刻の核心とした作家である。
文夫にとって彫刻とは、「見ることの訓練」であった。筋肉、骨格、重心、姿勢は徹底的に分析され、造形として確定される。彼の彫刻は、完成によって真理に近づこうとするものであり、本質的に「対座」の彫刻である。
一方、朝倉響子はこの父の写実を拒否したわけではない。彼女の人体表現には、明らかに父の教えが深く刻み込まれている。身体構造の理解、姿勢の破綻のなさは、文夫の厳格な教育なくして成立しえない。しかし決定的な違いがある。それは、完成に対する態度である。
文夫が完成によって彫刻の価値を確定させたのに対し、響子は完成がもたらす権威性を警戒した。形が完成した瞬間、像は語り始め、鑑賞者に対して優位に立つ。彼女はその関係を拒んだ。
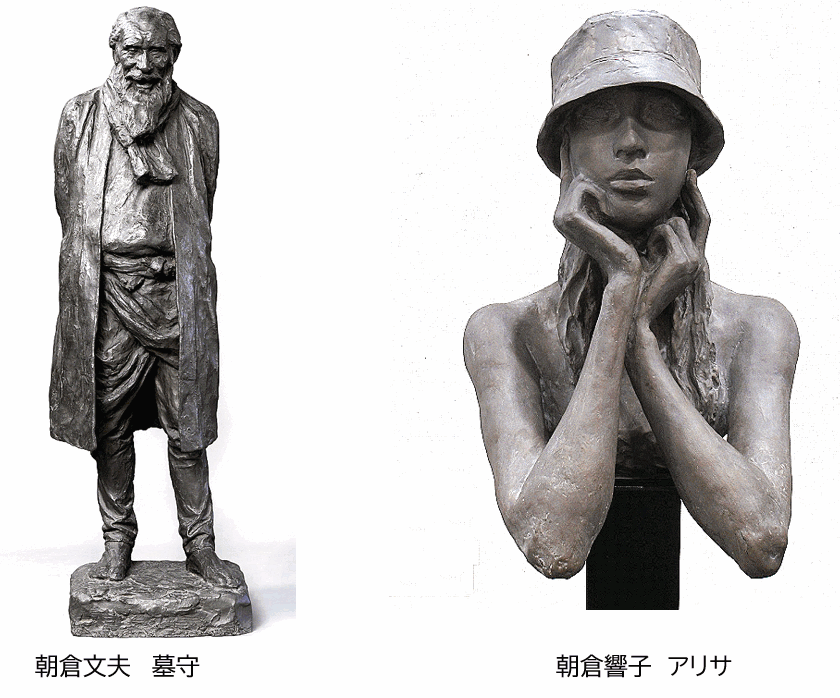
その結果として選ばれたのが、未決定性である。これは技術の不足ではない。完成を知った者による、意識的な拒否である。父が築いた写実の体系を内側から引き受けたうえで、娘はその体系を「同座」へと転換した。
ここに見られるのは反逆ではなく、成熟である。語る彫刻から、黙する彫刻へ。対座から、同座へ。朝倉響子は、父の彫刻が到達できなかった関係性を、別の方向から切り拓いたのである。
6.結論 ― 朝倉響子の信念
朝倉響子の彫刻に通底する信念は、次の一点に集約される。
彫刻は、人の時間を奪ってはならない。
彼女は、彫刻を「何かを伝える装置」にしなかった。代わりに選んだのは、主張せず、決めず、生活の流れを妨げないかたちで人と共に在ることであった。
その結果として生まれた彫刻は、不思議に居合わせ、静かに同座し、気持ちのよさだけを残す。それは弱い表現ではない。公共空間に存在する彫刻が到達しうる、最も誠実で、最も成熟したかたちである。
朝倉響子の彫刻は、同座する。その態度こそが、彼女の揺るぎない信念なのである。