佐藤忠良の風雅の誠 ― 同座する彫刻

日本文化の根本には、「対象に向き合う」のではなく、対象に意味や価値を与える側に立たないという姿勢がある。
その典型が、松尾芭蕉のいう「風雅の誠」である。「松のことは松に習へ、竹のことは竹に習へ」という言葉は、自然を観察し解釈する態度ではない。作者自身の考えや感情を前に出さず、身を外に置くことを要請する態度である。ここでは、作者は前に出ない。松が松として在る、その在り方に同座すること自体が、すでに表現となる。
古池や 蛙飛びこむ 水の音
この句は、解釈や感情を誘導しない。読む者は、意味を与える立場に立つことを許されず、いつのまにかその立場の外へと退かされる。そこにあるのは、場と出来事と音だけであり、読む者はそれらと同じ条件に置かれて「同座」する。
この思想は、俳諧にとどまらず、日本の絵画や工芸、美術全般に通底する。たとえば長谷川等伯の「松林図屏風」において、描き手は自然を構成的に把握する主体ではない。作者の考えや意図を前に出さず、自らは一歩引くことで、霧と余白のなかに松林そのものが立ち上がる場を成立させている。ここに見られるのは、日本文化に固有の「同座」という立ち位置である。

この「同座」という座標を、彫刻マトリックスとして〈対座/同座〉×〈価値を問う/価値をあたえる〉の二軸で捉えるならば、佐藤忠良の位置は明確である。彼は一貫して「同座・価値をあたえる」という象限から動かなかった。
佐藤忠良の彫刻は、見ていて気持ちがいい。それは装飾性や感情表現の豊かさによるものではない。彼の人物像は、過剰な身振りや象徴を排し、立つ、座る、うつむくといった最低限の姿勢にとどまる。
しかし、その静けさは、人間が人間としてそこに在ることを、否定することなく受け止めている。ここで彫刻は、鑑賞者に問いを突きつけない。意味や解釈に先立って、存在そのものがすでに正しい位置に置かれており、その前提が作品全体を静かに貫いている。
注目すべきは、佐藤忠良がこの日本的立ち位置を、形式的な「和」によって示さなかった点である。彼の彫刻語法は明らかに西洋近代彫刻の系譜に属し、人体の量感、構造理解、マッスの処理は国際的に共有可能な表現である。
その転機となったのが、「群馬の人」である。佐藤忠良が初めて広く評価され、その後の制作の起点となったこの作品には、同座の姿勢が明確に表れている。

群馬の人
そこに内在する倫理は、日本文化の「風雅の誠」、すなわち同座の精神と深く響き合っている。表現は西洋的であり、立脚点は日本的なのである。
この点において、佐藤忠良がフランスで個展を開催できた理由は明確である。西洋の鑑賞者は、理解可能な造形の内部に、主体が前に出ない、静かで異質な価値観を見出した。
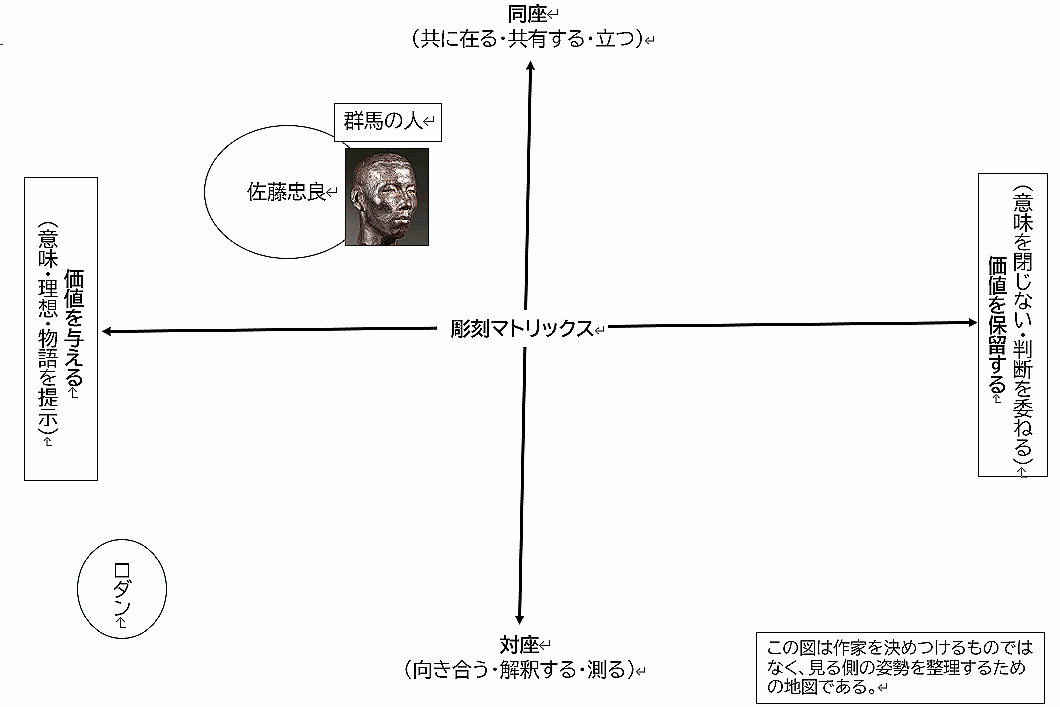
それは、西洋から見た日本文化・日本芸術の本質―対象を支配せず、意味や価値を与える立場から退くことで価値を生み出す態度―が、彫刻として可視化された瞬間であった。
結論として、佐藤忠良の彫刻は、松尾芭蕉のいう「風雅の誠」を、三次元造形において静かに実践した仕事であると考える。
佐藤の彫刻は、鑑賞者に意味や価値を即座に要求しない。まず像と同座する場を成立させ、その沈黙の持続のなかで、美は語られることなく、しかし確かに回復される。
それは、価値を主張する美ではない。また、価値を放棄した無意味の美でもない。同座を引き受けた者にのみ、後から立ち上がる美である。
この「価値を語らずに美を回復する」という不動の姿勢こそが、佐藤忠良の彫刻を時代や解釈から自由なものとし、今なお多くの人にとって説明を要しない「気持ちのよさ」を保ち続けている理由である。