都市生活における沈黙と現実主義 ― 淀井敏夫
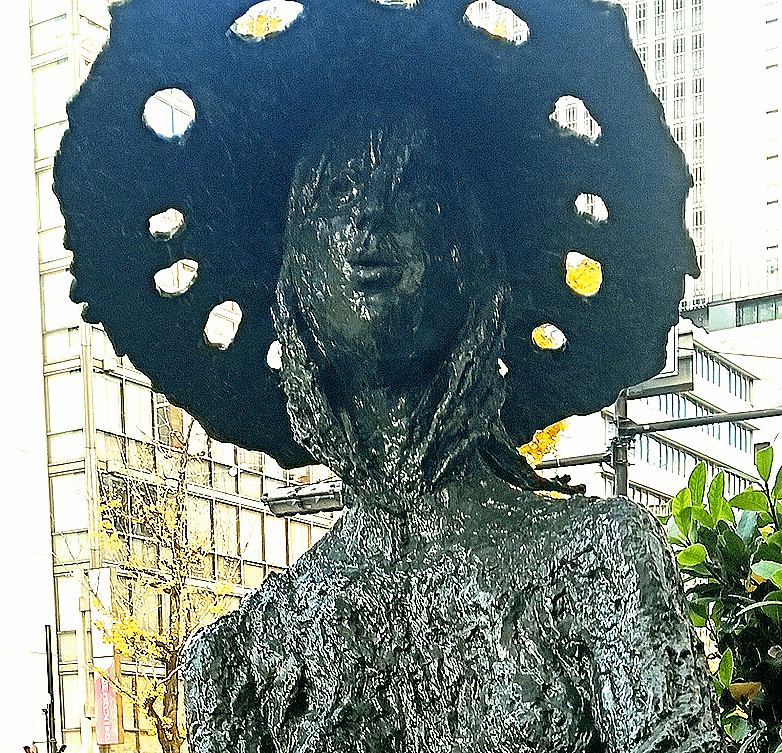
序論――違和感としての出会い
大阪御堂筋で朝倉響子の「ジル」に出合った後で、その作品はあった。淀井敏夫の「渚」である。若い女性が長い脚を組み、大きな帽子をかぶって腰かけている姿は、一見すると都市彫刻として穏やかで、特別に挑発的な要素を持たないように見える。
しかし近づくにつれて、私はある違和感を覚えた。表面は滑らかに整えられておらず、石膏を付けた痕跡がそのまま残されている。御堂筋という、スピード・洗練・効率が支配する都市空間に置かれているにもかかわらず、作品の周囲だけ、空気の密度が異なるように感じられたのである。
朝倉響子の作品の前では、身体が自然に緩み、すぐに安心感が立ち上がった。それに対して「渚」の前では、安心でも不安でもない、一瞬判断が止まった感覚が生じた。この違和感は拒絶ではない。むしろ、頭の中の理解する回路が一時的に止まった。今回は、この感覚を出発点として、淀井敏夫の彫刻作品を「都市生活における沈黙と現実主義」として捉え直す試みである。
Ⅰ なぜ淀井の作品は理解しにくいのか
淀井の作品が難解に感じられる理由は、単に抽象的だからでも、技巧的だからでもない。主に次の三点に集約できる。
第一に、物語や主題が提示されないこと。
第二に、完成された理想像が示されないこと。
第三に、作品が鑑賞者に意味の受け取り方を指示しないこと。
多くの彫刻は、鑑賞者が「どう見ればよいか」を暗黙のうちに示す。しかし淀井の作品は、その入口を用意しない。そのため鑑賞者は、作品の意味が分からないので、最初は自分自身の態度を探らなければならないことになる。このことこそ、淀井作品の理解を難しくしている最大の要因である。
Ⅱ 「同座・価値をあたえる」という共通基盤
ここで重要となるのが、「同座・価値をあたえる」という彫刻マトリックスの考え方である。これは、作品が鑑賞者に意味解釈や価値判断を要求するのではなく、同じ空間・同じ時間に存在する(同座)こと自体によって価値が成立するという立場を指す。
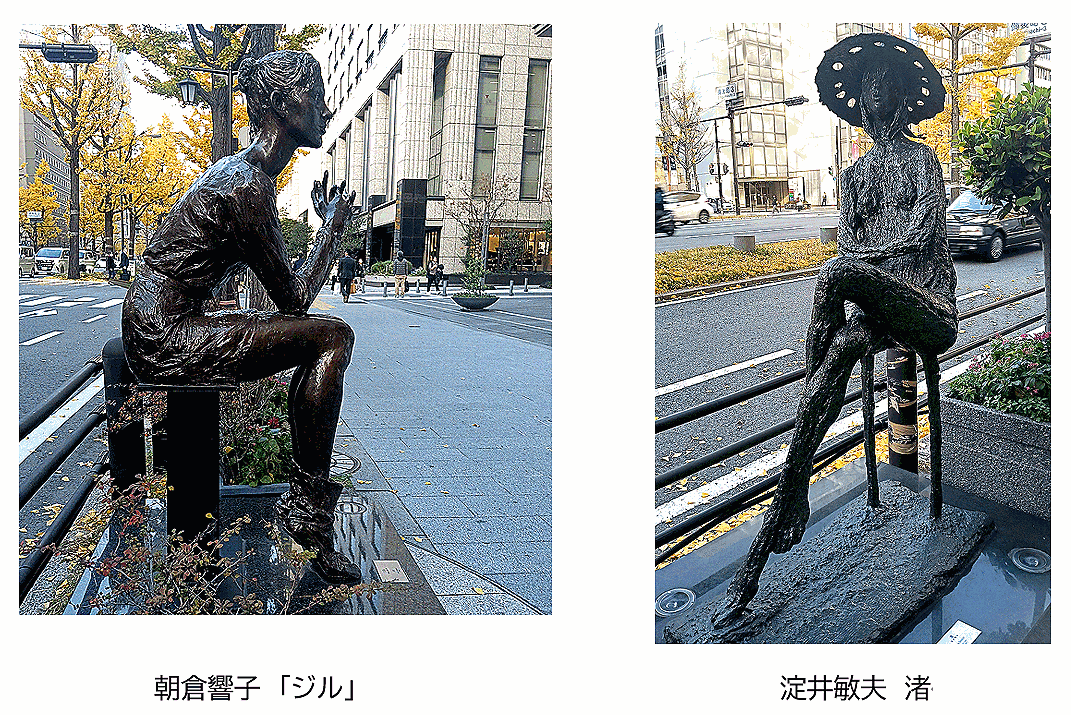
朝倉響子と淀井敏夫は、ともにこの立場に立っている。両者の作品はいずれも語らず、教えず、説得しない。まず像がそこに在り、鑑賞者はしずかにその存在と同座する。価値は説明によって与えられるのではなく、態度としての存在から静かに生じる。
しかし、同じ「同座」であっても、その質は一様ではない。ここにこそ、両者を分ける決定的な差異がある。
Ⅲ 彫刻マトリックスの再定義――同座の内部差異
本稿で用いる彫刻マトリックスは、これは作家を対立的に分類するための図ではない。鑑賞者が作品とどのような態度で関わることになるのかを整理するための座標系である。
朝倉響子と淀井敏夫は、ともに「沈黙」の側に位置する。どちらの作品も意味や主張を語らない。しかし、沈黙の質が異なる。
朝倉響子の作品は、沈黙の中にあっても、鑑賞者が比較的早い段階で価値を受け取ることができる地点にある。像の姿勢は安定しており、緊張は解かれている。鑑賞者はその姿勢と同座することで、「ここに居てよい」「この状態に身を委ねてよい」という安心を即座に感じ取る。ここで与えられる価値は、すでに整った状態と同座できたという経験である。
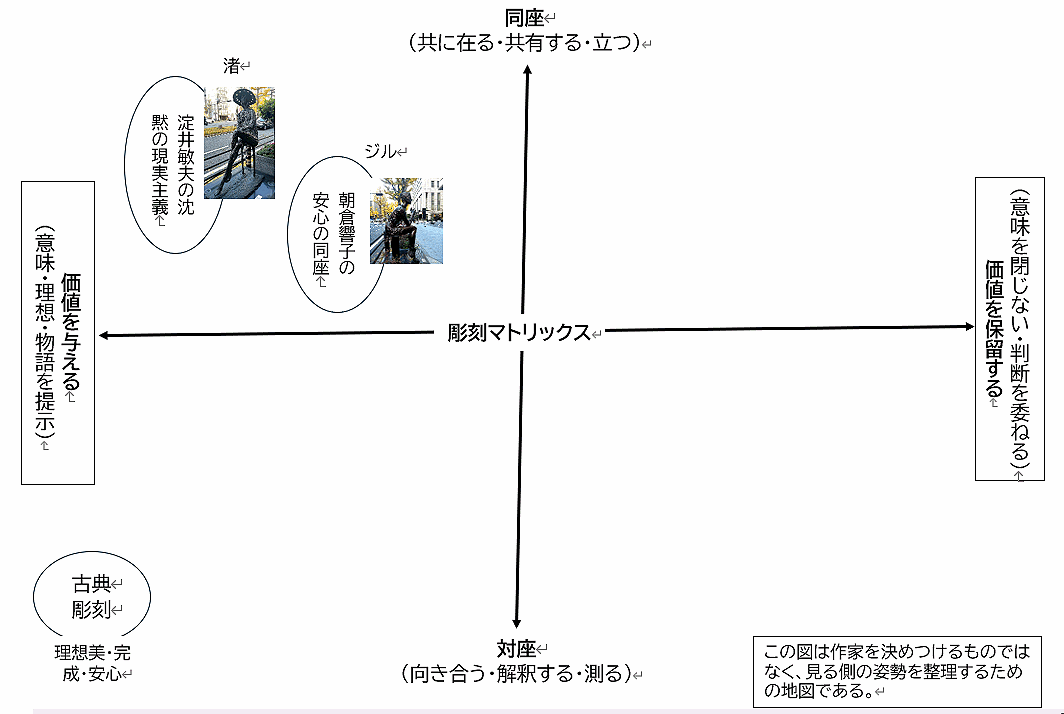
一方、淀井敏夫の作品も沈黙の側に立ちながら、その位置はより「現実」に近い。像は語らないが、安心や理想像を先に差し出さない。表面には制作の痕跡が残され、姿勢には摩擦や緊張が含まれている。同座することは許されるが、「どう受け取ればよいか」という意味は即座には与えられない。価値は確かに発生しているにもかかわらず、判断は観察者の側に委ねられる。
朝倉の彫刻が示しているのは、すでに気持ちや状況が落ち着き、「この状態でよい」と受け入れられている、安心して腰を下ろしていられる身体の状態である。一方、淀井の彫刻が示しているのは、まだ落ち着ききらないまま、それでもその場に身を置き続けている身体の状態である。
ここで問題にしているのは、彫刻の姿勢そのものではなく、都市生活の現実に対して、自分がどのような身の置き方をしているのかということに、一瞬気づくかどうかという点である。
Ⅳ 制作技法と現実主義の生成
淀井の現実主義は、思想として語られる前に、制作技法そのものに組み込まれている。心棒に直接石膏を付けていく手法では、完成形を先に固定することができない。均整や滑らかさは結果として現れるものであり、最初の目的ではない。
付けては判断し、修正し、それでも残る痕跡を引き受ける。この反復は、生きることのプロセスと極めて近い。理想通りには進まず、無駄や抵抗を含みながら、それでも続いていく。その結果として現れる形には、生き続けるために生成されたエネルギーが宿る。
《鴎》において示されているのは、成功や解放が保証されない状況の中で、それでも身体の向きが上へ向かっているという意味での「上昇」である。
《渚》においては、進む理由も退く理由も定まらないまま、その場に身を置き続けているという意味での「滞留」が示されている。
また、《エピダウロス・追想》において人物が手にしている仮面は、役割や演技を象徴するものである。しかしこの仮面は被られていない。拒絶されてもおらず、ただ使われずに保持されている。この位置関係が示しているのは、社会的な役割を十分に理解したうえで、いまはそれを演じないという選択である。ここでの直立とは、役割から解放された理想的主体を示すものではなく、役割を引き受ける可能性を残したまま、それでも崩れずにそこに在る身体のあり方を指している。
これらはいずれも、完成や解決に向かうのではなく、制作の過程そのものが途切れずに続いた結果として現れた形態である。そのため、ここにある力は祝祭的な生命賛歌ではなく、きびしい現実の中で折れずに持続している力として理解される。
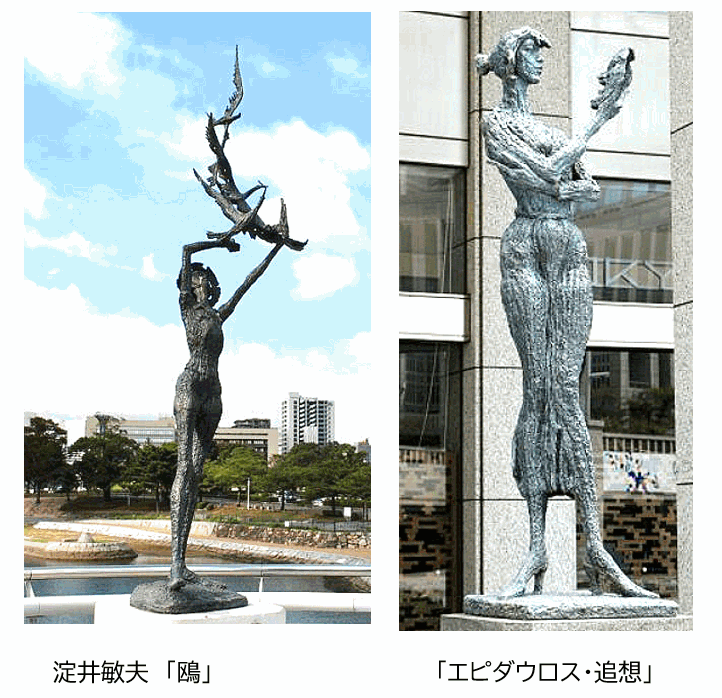
Ⅴ 観察者に起きること――結果としての内省
淀井の作品は、鑑賞者に内省を促すことを目的としていない。しかし、作品の前に立った観察者は、ほとんど不可避的に現実の自らの立ち方を意識してしまう。
像が、この速度、この緊張、この距離感で都市の中に立っていることに出会ったとき、観察者は無意識のうちに自分自身の姿勢と比較してしまう。ここで省みられるのは、鑑賞態度ではなく、都市生活の中での自分の在り方である。
重要なのは、この内省が目的ではなく、結果として生じるという点である。像が沈黙のまま現実を引き受けた姿勢で立っているがゆえに、観察者の側に変化が起きる。
結論――都市生活における沈黙の現実主義
淀井敏夫の彫刻は、都市生活における沈黙の現実主義として、まずそこに立っている。理想を掲げず、語らず、しかし現実を十分に理解した姿勢で立っている。
その結果として、観察者はおのずと自らの立ち方を省みる。この「結果としての内省」こそが、淀井作品の最も重要な効能である。それは啓発でも教育でもない。ただ、別の立ち方がすでに実行されている事実に出会うことによって生じる変化である。
都市を変えようとせず、人を教えようともしない。それでも、都市の中で生きる私たちの態度を、確かに一瞬変えてしまう。その静かな強度こそが、淀井敏夫の彫刻が持つ、現代都市における最も信頼できる力なのである。
2026年1月1日