理論編その2 彫刻マトリックスによるデュシャン後の現代彫刻の見方

はじめに――現代彫刻はなぜ「わからない」のか
私はこのHPで、これまで主に具象彫刻作品を見てきた。人物像や身体表現を通して、彫刻が人間や世界とどう向き合ってきたのかを考えてきたからである。しかし、パブリック・アートに目を向けると、そこには多くの抽象彫刻が展示されている。
正直に言えば、抽象彫刻は、あまりにもわかりにくいものがある。たとえば、旭川彫刻美術館で見た「GARONNEの旅から」という作品の前に立ったとき、私は言葉を失った。ただ黙って立ち尽くし、腕を組み、「むう……」とうなるばかりであった。美しいとも、嫌いだとも、意味があるとも言えない。何をどう受け取ればよいのか、まったく見当がつかなかったのである。
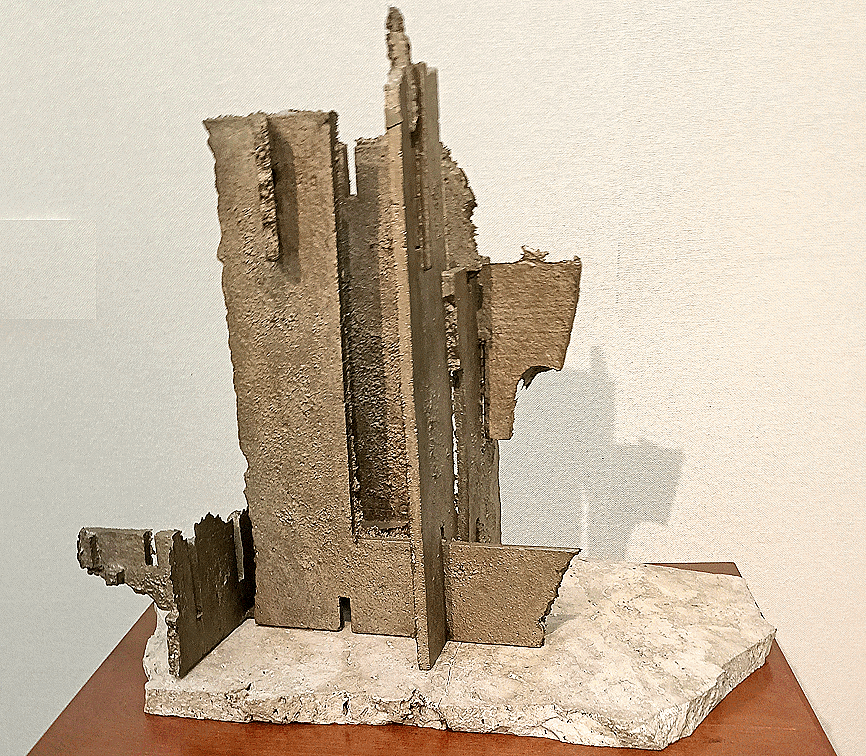
この体験は、私だけの特殊なものではないだろう。多くの鑑賞者が、抽象彫刻の前で同じような戸惑いや不安を抱えているのではないかと思う。「わからない」「どう見ればいいのかわからない」その感覚こそが、抽象彫刻を前にしたときの、もっとも率直な反応ではないだろうか。
そこで私は考えた。この「わからなさ」は、避けるべきものなのか。それとも、抽象彫刻が鑑賞者に差し出している、ひとつの出発点なのか。
本稿では、この問いを手がかりに、抽象彫刻を「理解しようとする」のではなく、「どう関わるのか」という視点から、鑑賞のあり方を整理してみたいと考えている。
現代彫刻が「わからない」と感じられるのは、作品そのものが難解だからではない。むしろ、鑑賞者がどのような姿勢で彫刻と関わればよいのか、その前提が共有されていないことに原因がある。
多くの場合、私たちは彫刻を前にすると、「意味は何か」「美しいかどうか」「評価できるか」といった問いを、無意識のうちに立ててしまう。
しかし現代彫刻の多くは、そもそもその問いに答える構造を持っていない。その結果、鑑賞者は「わからない」「居心地が悪い」という感覚だけを抱え込むことになる。
本稿では、この「わからなさ」を、作品の欠点や鑑賞者の理解不足として片づけない。評価や解釈の問題としてではなく、鑑賞者と作品がどのような関係に置かれているのかという視点から、捉え直してみたい。
そのために用いるのが、私自身が整理した「彫刻マトリックス」である。このマトリックスは、彫刻を「対座/同座」・「価値を与える/価値を保留する」という二つの軸で捉えるものであり、作家や作品を固定的に分類するための図ではない。
この図が示すのは、「この作品は何を意味するのか」ではなく、鑑賞者が、いまどのような姿勢で作品と向き合わされているのかである。言い換えれば、鑑賞者自身の立ち位置を可視化するための地図である。
本稿ではまず、マルセル・デュシャンを、現代彫刻理解の起点として位置づける。彼が切り開いた「価値保留」という地点は、以後の現代彫刻が避けて通れなくなった出発条件である。
そのうえで、デュシャン以後の作家たちが、この「価値保留」をどのように引き受け、あるいは、どのように別の方向へ進めようとしたのかを、具体的な作品とともに見ていく。
抽象彫刻の前で立ち尽くしたときの「わからなさ」は、ここからはじまる。それは失敗ではなく、現代彫刻に向き合うための、正しい入口なのである。
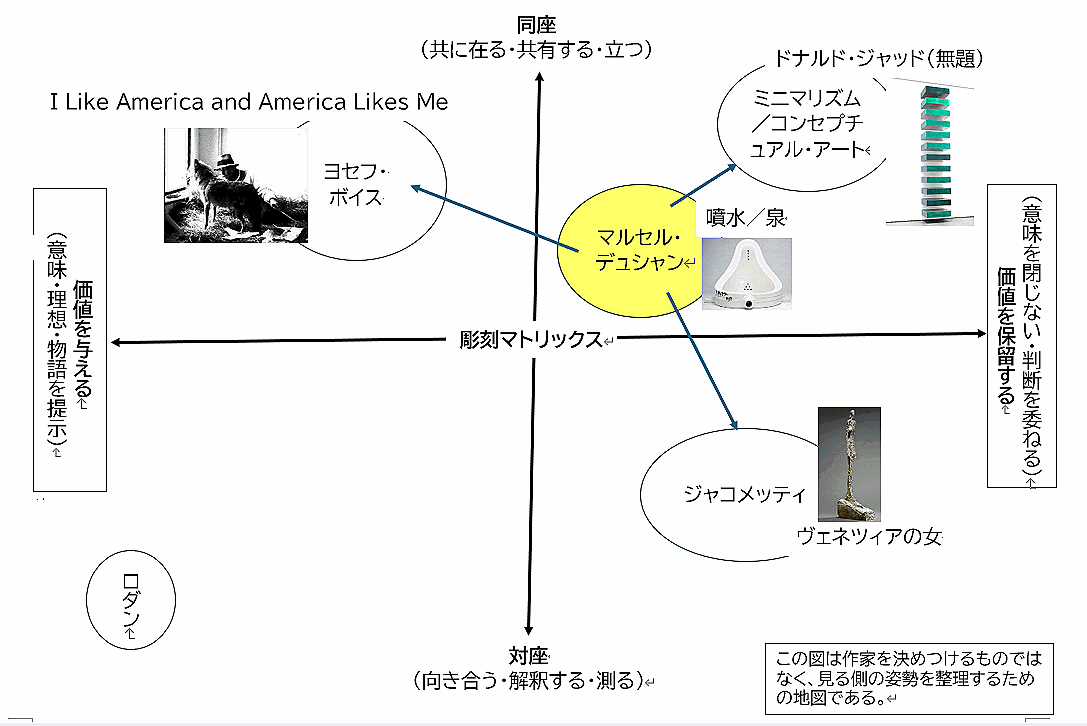
1. 「価値をどう回復するか」という問いの意味
ここで言う「価値の回復」とは、理由ははっきりしないが、なぜか大切だと感じてしまう状態を、もう一度どう成立させるかという問いである。それは、美の基準や正解を与えることではない。
現代彫刻の前に立ったとき、私たちはときどき、
●これは無関係ではない
●ここを通り過ぎてはいけない気がする
●もう少し、この場に留まっていたい
と感じることがある。本稿で扱う「価値」とは、このような説明できないが、確かに起きている感覚のことである。
マルセル・デュシャン以後、芸術は「価値をあらかじめ示さない」ことを、ひとつの態度として引き受けてきた。作品は意味や美を説明せず、鑑賞者は自分で判断するしかない状況に置かれる。
その結果、「これは良い作品だ」「これは大切だ」と決めつけられることは少なくなった。一方で、鑑賞者は作品の前で、「何を感じ取ればよいのかわからない」「どう関わればよいのかわからない」という戸惑いも抱えるようになった。
ここで生じたのが、「価値をどう回復するか」という問いである。それは、失われた価値を取り戻すという話ではない。何も説明されていないのに、なぜか心が引き止められてしまう瞬間を、どう考えればよいのかという問題である。
重要なのは、「回復」という言葉を、元に戻すことだと誤解しないことである。近代彫刻が行ってきたように、理念や象徴を示し、「これは重要だ」と教える方法は、もはや通用しない。
いま問われているのは、価値を語らない。価値を押し付けない。それでもなお、鑑賞者が立ち止まり、向き合い、関係を引き受けてしまうような状態を、彫刻はいかにつくり出すのか、ということである。
この問いを手がかりに、本稿では、
●価値を保留したまま同座させる彫刻
●対座を強いることで価値が生じてしまう彫刻
●そして、倫理として価値を引き受けさせる彫刻へと、
議論を進めていく。
2. デュシャンと「同座・価値保留」
デュシャンの《噴水/泉》は、彫刻に価値を与えないことを、はじめて意図的に成立させた作品です。この作品がもたらしたのは新しい造形ではなく、価値判断そのものを宙づりにする状況でした。
マルセル・デュシャンの《噴水/泉》は、既製の男性用小便器を逆さに置いただけの作品である。そこには造形的工夫も、象徴的意味も、美的主張も存在しない。彫刻として「見るべき点」は、ほとんど何も提示されていない。
このとき作者は、価値を語ることを完全に放棄している。「これは美しい」「これは意味がある」といった判断は、一切示されない。鑑賞者は、説明も導きもないまま、作品と同じ空間に立たされるだけである。
重要なのは、ここで鑑賞者が作品と向き合っているとは言い難いという点である。この小便器は、感情を喚起せず、理解を促さず、鑑賞者を呼び止める力も持たない。鑑賞者は、対話することも、対座することもできず、ただ「そこに在るもの」と同じ場に置かれる。
彫刻マトリックス上で見れば、「噴水/泉」は明確に「同座・価値保留」の位置にある。
ここで生じているのは、価値の否定ではない。価値判断の前提そのものが解体されているのである。何をもって彫刻と呼ぶのか、誰が価値を決めるのか、芸術とは何か。その問いは作品の内部ではなく、美術制度そのものへと向けられている。
したがって、この作品の衝撃は、彫刻の形態にあったのではない。鑑賞者や美術館、批評家が当然のように依拠してきた「美術には価値があるはずだ」という前提を、根底から揺さぶった点にある。
ただし、この地点において、価値はまだ回復されていない。鑑賞者は「わからない」「判断できない」という状態に置かれたままであり、そこから先へ進むための手がかりは与えられていない。
その意味で、「噴水/泉」は現代彫刻の完成形ではない。むしろ、現代彫刻が避けて通れなくなった出発条件を示した作品である。
デュシャンは、「価値を与えない彫刻」「同座したまま、判断を保留させる彫刻」という地点を、不可逆的に切り開いた。
以後の現代彫刻は、すべてこの地点を前提にせざるを得ない。
そこにとどまる(ドナルド・ジャッド)のか、そこから対座へ進む(アルベルト・ジャコメッティ)のか、あるいは倫理を引き受ける(ヨーゼフ・ボイス)のか。デュシャンの「噴水/泉」は、その分岐点を初めて明確に示した作品なのである。
3. 価値保留を安定させた彫刻―デュシャンの地点にとどまる系譜
デュシャン以後の多くの現代美術は、この「価値保留」の地点に意図的にとどまった。ドナルド・ジャッドやソル・ルウィットに代表されるミニマリズム/コンセプチュアル・アートは、
●意味を語らない
●美を提示しない
●判断を鑑賞者に委ねる
という態度を徹底した。
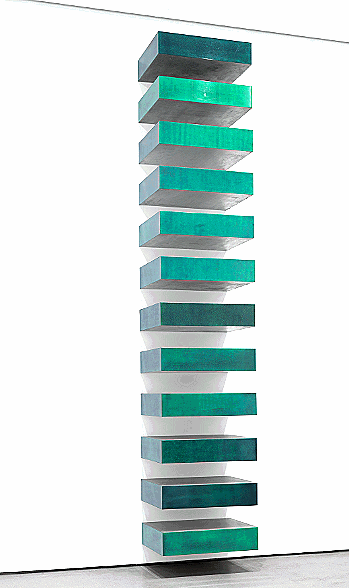
ドナルド・ジャッド《無題(スタック)》シリーズ(1960年代)
壁面に等間隔で配置された直方体ユニット
●作家の手の痕跡や象徴性を排除
●「表現」ではなく「存在の事実」だけが提示される
●この作品では、意味・物語・感情は語られず、鑑賞者はただ同じ空間に立たされる。
結論から述べます。鑑賞者は、そのまま「わからない」「不安だ」という状態でいてよい。ただし、それは投げ出してよいという意味ではありません。判断を急がず、その場に留まることが、この彫刻に対する正しい関わり方です。
壁面に等間隔で配置された直方体ユニットの作品は、作家の手の痕跡や象徴性を徹底して排除している。そこに示されているのは「表現」ではなく、ただ存在しているという事実だけである。意味や物語、感情は語られず、鑑賞者は説明も手がかりも与えられないまま、作品と同じ空間に立たされる。
このとき多くの鑑賞者は、「何を見ればいいのかわからない」「不安になる」「評価できない」と感じる。しかし、この反応は失敗ではない。むしろ、作品が意図どおりに機能している証拠である。
この作品は、デュシャンが切り開いた「価値保留」の地点を、造形として安定化させた例である。価値を放棄しているのではなく、価値判断の前提そのものを解体している。そのため、鑑賞者は「理解する」「感動する」「意味を読み取る」といった、これまで当たり前だと思っていた鑑賞の姿勢を使うことができない。
重要なのは、ここでの「わからなさ」は、知識不足や感受性の欠如を意味しないという点である。この作品は、学べばわかるようになる構造を最初から持っていない。したがって、わからないまま立たされること自体が、この彫刻の到達点である。
では、鑑賞者は何をすればよいのか。答えは意外に単純である。何もしなくてよい。ただし、「早く意味をつかもう」「評価を下そう」とせず、その場に留まり続ける。
この彫刻が鑑賞者に求めているのは、解釈や感想ではない。判断を保留したまま、同じ空間と時間を引き受ける態度である。わからない、不安だという感覚を消そうとせず、その状態のまま立ち続けることが、ここでは唯一の鑑賞行為となる。
もっとも、この地点には限界がある。この「同座・価値保留」の場では、価値は回復されない。倫理も、まだ立ち上がらない。鑑賞者は宙づりのままに置かれ続ける。
しかしそれは欠点ではない。この宙づりの状態を、意図的に制度化したこと自体が、この作品の意味である。
そして、この限界があるからこそ、次に「価値を引き受けさせる彫刻」――すなわちボイスのような倫理の彫刻が、必然的に現れてくる。
現代彫刻において、「わからないままでいること」は逃避ではない。それは、価値判断以前の地点にとどまるという、きわめて積極的な態度なのである。
4. 身体と実存による回収―価値保留から〈対座〉へ
一方で、彫刻の内部から「価値を保留したままでは、彫刻は成立しない」という危機感も生まれた。その代表例が、「アルベルト・ジャコメッティ」である。
ジャコメッティは、デュシャン以後の意味の不在を引き受けつつ、人間存在そのものを主題に戻した。彼の彫刻は、理念としての価値を語らない。しかし、痩せ細った身体や不安定な立ち姿は、鑑賞者に逃げ場のない問いを突きつける。

ジャコメッティ 《ヴェネツィアの女》シリーズ(1956)
●極端に細長い身体
●動かない直立姿勢
●表情や物語をほぼ剥奪した造形
この女性像は、意味や美を語らないにもかかわらず、鑑賞者に価値判断を引き起こしてしまう彫刻です。その力は説明や象徴からではなく、人間が「そこに在る」という事実の重さから生まれています。
アルベルト・ジャコメッティの女性像は、美しさも象徴も提示しません。物語や感情を読み取る手がかりもほとんど与えられない。ただ、細く引き伸ばされた身体が、直立したまま、こちらを向いて立っているだけです。
しかし、足だけは大きくしっかりとこの大地(地球)に立っているのです。
鑑賞者は、その像を前にして、不思議な圧力を感じます。「何を表しているのか」はわからない。それでも、「目を逸らしてよい存在ではない」と感じてしまう。ここで起きているのは、理解ではなく、否応なく向き合わされる経験です。
この作品では、意味は最後まで語られません。その点で、ジャコメッティはデュシャン以降の「価値保留」を引き受けています。しかし同時に、この像は、鑑賞者を強く呼び止め、正面から向き合わせる。
彫刻マトリックス上で言えば、
●意味は与えられない
●しかし鑑賞者は、距離を保ったままではいられない
この点で、ジャコメッティの女性像は、最初から「価値を与える」位置に立っているわけではありません。むしろその出発点は、徹底した「対座・価値保留」にあります。
この像は、「これは何を意味するのか」「なぜ美しいのか」といった問いに対して、いかなる答えも提示しません。象徴も物語も拒み、価値判断の手がかりを意図的に奪います。鑑賞者はまず、理解も評価もできないまま、像と正面から向き合わされることになります。
しかし、ここで奇妙な逆説が生じます。価値が語られていないにもかかわらず、鑑賞者は「これは人間だ」「ここに立っているという事実が重い」と感じてしまうのです。
つまり、価値は作品の内部にあらかじめ用意されているのではありません。鑑賞者が、その沈黙する存在と逃げ場のないかたちで対座した瞬間、関係の中で、否応なく発生してしまうのです。
このとき鑑賞者は、理解できなくても、評価を保留したままでも、すでに作品と向き合ってしまっています。向き合ったという事実だけは、もはや取り消すことができません。
その意味で、ジャコメッティの女性像は、「対座・価値保留」を徹底した結果として、彫刻を部分的に「対座・価値が生じてしまう」位置へと押し戻しています。
ここで生まれる価値は、美や象徴ではありません。人間が、意味も保証もない世界の中で、それでも立ち続けているという事実そのものの重さです。
ジャコメッティの彫刻は、その重さを、説明することなく、沈黙のまま鑑賞者に引き渡します。だからこそ、この女性像は説明を拒みながら、強く記憶に残るのです。それは、価値を語らないことによって、結果として価値を生じさせてしまう彫刻だと言えるでしょう。
だからこそ、この女性像は説明を拒みながら、強く記憶に残る。それは、価値を語らないことで、かえって価値を発生させる彫刻なのである。
5. 倫理としての価値回復 ― 社会・行為・関係性の彫刻
別の方向から価値を回復した作家が、ヨーゼフ・ボイスである。ボイスは、造形物ではなく、行為・言葉・社会参加そのものを彫刻と捉えた点で、デュシャンの思想を強く継承している。
しかし彼は、価値を完全には保留しなかった。「誰もが芸術家である」「社会彫刻」という概念が示すのは、価値判断の放棄ではなく、価値を引き受ける主体の拡張である。それは、デュシャンが「芸術とは何か」を問う構造を破壊したのに対して、ボイスは「その問いを社会と倫理の次元へ拡張」したのです。ボイスはデュシャンを模倣したのではなく、デュシャンによって開かれた〈芸術の空白〉を、社会的・倫理的実践で埋め直したのです。
ボイスの彫刻において回復される価値とは、美的完成度ではない。それは、関わることから逃れられないという倫理的重さである。言い換えれば、倫理とはここで、引き受ける態度ということ。

ヨセフ・ボイス 《I Like America and America Likes Me》(1974)
●コヨーテと数日間、同じ空間で過ごすパフォーマンス
●彫刻=関係性が生成される場
●意味の説明は最小限だが、「共に在る」こと自体が倫理的価値を帯びる
この作品において重要なのは、何を象徴しているかではない。鑑賞者が、この関係性をどう受け止め、どう距離を取るのかという態度そのものが問われている点である。
位置づけ:同座・価値を与える(倫理=引き受ける態度)
デュシャンの価値保留を前提にしつつ、それを共存と関与の重さとして引き受け、価値を回復した。
彫刻マトリックス上では、ボイスは明確に「同座・価値を与える(倫理として)」の位置に置かれる。
ボイスは、
●デュシャンの価値保留を前提に
●造形から行為・関係・社会へと価値の重心を移し
●その結果、同座のまま価値を回復した作家である。
したがって、彼の重要作のすべては、「彫刻=倫理が立ち上がる場」を示している。
わかりやすく言えば、ボイスにとって彫刻は、目で鑑賞し理解する対象ではない。
ボイスにとって彫刻とは、完成した「物」を鑑賞する対象ではありません。それは、人が世界や他者とどう関わるべきかを、自ら引き受けざるを得なくなる状況をつくる行為です。
彼の作品は、美しさや意味を説明しません。代わりに、鑑賞者を不安定で判断のつかない場に置きます。そこで問われるのは、「これは何か」ではなく、「あなたは、この状況にどう関わるのか」という姿勢です。
このとき立ち上がるのが、ボイスの言う「倫理」です。それは道徳的な教訓でも、正解の提示でもありません。自分は無関係ではいられない、判断を他人に委ねられない、そう気づいた瞬間に生じる、引き受けの意識そのものです。
つまりボイスの彫刻とは、価値や意味を与える作品ではなく、鑑賞者が自らの責任を自覚してしまう場なのです。
私は、この点にボイスの彫刻の核心があると考えます。彼は彫刻を、美の対象から、人間が倫理的存在として立ち上がるための装置へと転換しました。そこに、現代彫刻としての決定的な意義があります。
この点において、ボイスの彫刻は、今日においてもなお有効な思想的実践です。
6. 同座のまま価値を回復する―日本彫刻の特異な到達点としての柳原義達
デュシャン以後、彫刻において「価値を与える」という行為は、根本から問い直されてきた。意味や美を作品に内在させることは疑われ、価値判断は保留されるべきものとされた。やがてボイスに至り、価値は造形の内部から離れ、社会的行為やプロセスへと拡散していく。この流れのなかで、造形そのものの場において、しかも権威的でも説明的でもないかたちで価値を回復することは、現代彫刻にとって最も到達困難な課題の一つとなった。
この困難な地点に、日本彫刻の内部から独自のかたちで応答した作家が柳原義達である。ただし、その応答は直線的な発展ではない。柳原の仕事の本質は、同座と対座を往復しながら、最終的に「同座のまま価値を回復する地点」に至った思考の軌跡にある。
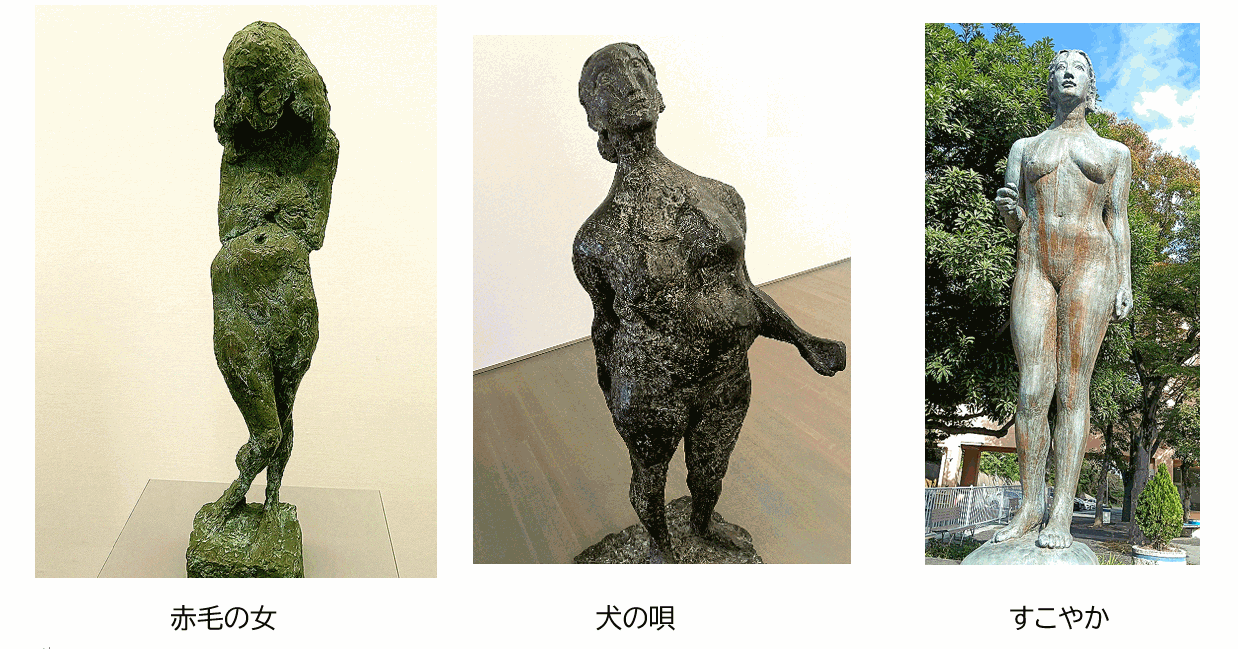
柳原の初期作品「赤毛の女」において、彫刻はすでに「同座」の関係に立っている。この像は、明確な物語や感情を語らない。身体はねじれを含みつつも、抵抗や主張として読み取れる表現には至らず、鑑賞者は「何を表しているのか」を解釈する足場を与えられない。鑑賞者は像と向き合うが、意味を与える側にも、評価する側にも立つことができず、ただ同じ場に立ちすくむ存在として置かれる。
ここで成立しているのは、同座ではあるが、価値はまだ回復されていない状態、すなわち「同座・価値保留」である。肯定も否定も与えられず、鑑賞者は判断を宙づりにされたまま、その場に留まらされる。この段階の柳原は、デュシャン以後の価値保留を、造形の内部で真正面から引き受けている。
続く「犬の唄」において、柳原の彫刻は明確に「対座」へと踏み出す。この像では、抵抗、不安、戦後的倫理といった感情が、身体表現としてはっきりと刻み込まれている。鑑賞者は像と向き合い、その緊張や意味を読み取ろうとし、感情的・倫理的応答を迫られる。ここでは、鑑賞者は再び「読む側」「判断する側」として立ち位置を回復している。
「犬の唄」は同座ではない。これは、対座を極限まで引き受けた彫刻であり、価値は不安定でありながらも、なお表現として前景化されている。柳原はここで、価値を保留したまま沈黙するのではなく、あえて「対座」へと身を投じることで、価値と倫理の緊張を造形として引き受けたのである。
しかし柳原の彫刻は、対座の緊張に留まらない。やがて造形は再び変化し、感情表現や象徴的身振りは次第に抑制されていく。形態は簡素化され、量感と姿勢そのものが前面に出る。この変化は、対話の放棄でも価値の断念でもない。むしろ柳原は、「意味を語らずに、なお造形は成立しうるのか」という問いを、より厳しいかたちで引き受けていったと考えられる。
その到達点として現れるのが「すこやか」である。「すこやか」において、像はもはや抵抗も不安も主張しない。鑑賞者に読み取るべき感情や物語は与えられず、判断や解釈を促す要素も前景化しない。鑑賞者は対座することができず、再び像と同じ場に立つ存在として置かれる。
ここで成立する「同座」は、「赤毛の女」と同じ同座ではない。「すこやか」においては、価値はもはや保留されていない。像の佇まい、過不足のない量感、静かな均衡は、「ここに在ることが肯定されている」という感覚を、造形そのものとして成立させている。
重要なのは、この価値が語られていないことである。外部から付与される価値でもなく、鑑賞者が判断によって獲得する価値でもない。同座を引き受けた鑑賞者の側に、遅れて、しかし確実に「立ち上がる価値として回復」されている。価値は主張されないが、否定もされていない。
この点において、柳原義達は、デュシャン以後の現代彫刻が最も到達困難だった地点に立っていると言える。価値を解体するのでもなく、社会へと拡散するのでもなく、古典的基準として復活させるのでもない。同座という関係を保ったまま、価値を回復するという、きわめて困難な態度を、造形によって示したのである。
「赤毛の女」における同座・価値保留、「犬の唄」における対座の極限、そして「すこやか」における同座・価値回復。この往復運動は、作風の変化ではない。鑑賞者の立ち位置そのものを変化させる造形的思考の軌跡である。
柳原義達の彫刻は、鑑賞のコペルニクス的転回―すなわち、意味や価値を与える主体から降り、像と同じ場に立つという立ち位置の転換―を引き受けた後にのみ可能となる、日本彫刻の特異な到達点を、静かに、しかし決定的に示している。。
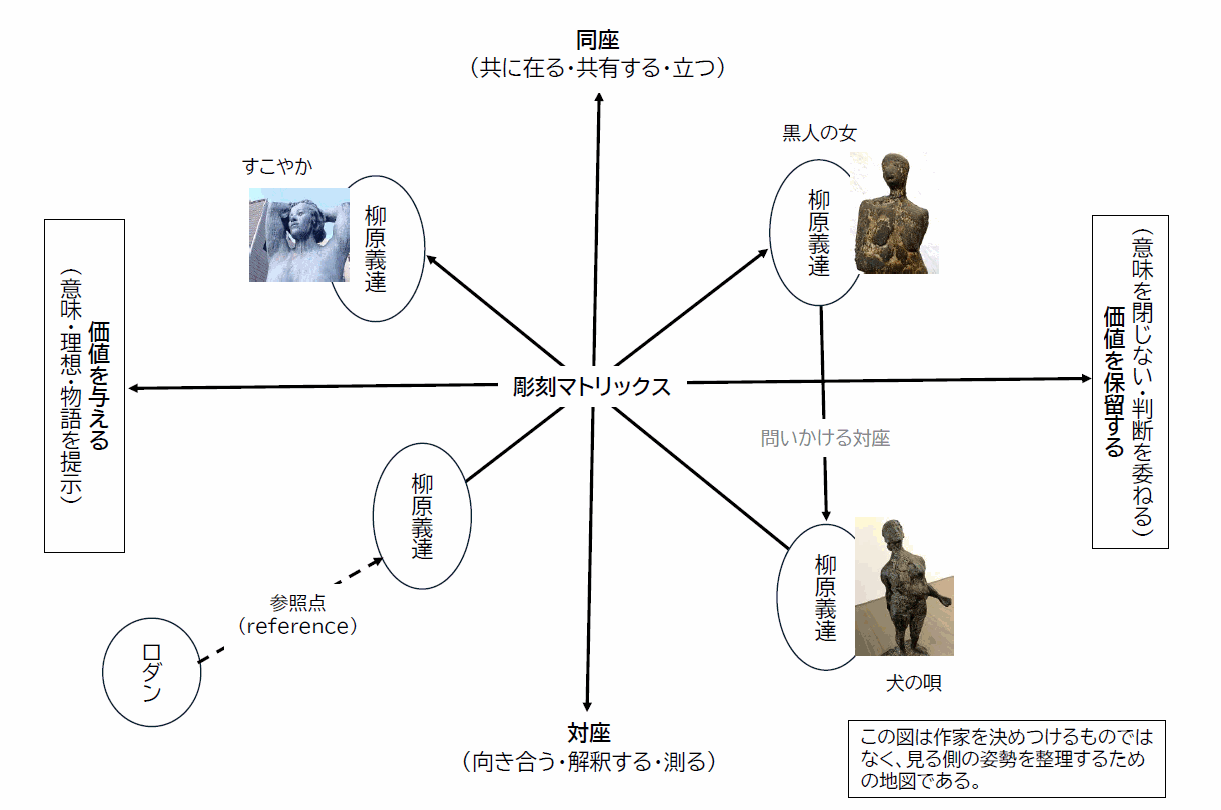
これは、デュシャン以後の現代彫刻が最も到達困難だった地点だと言える。
おわりに―見る側の成熟としての現代彫刻理解
デュシャン以後の現代彫刻は、
●価値保留を安定させた流れ
●身体によって対座を回復した流れ
●倫理として価値を再導入した流れ
●同座のまま価値を与えるという到達
という複数の道を歩んできた。
したがって、デュシャンは現代彫刻を解放した英雄でも、破壊者でもない。現代彫刻に「価値をどう回復するか」という長い宿題を残した起点なのである。
現代彫刻を理解するとは、作品を理解することではない。自分自身が、どの位置から彫刻を見ているのかを理解することである。彫刻マトリックスは、そのための有効な道具であり、現代彫刻を「わからないもの」から、「位置の異なる思考の実践」へと変換する。
この地点に立ったとき、現代彫刻はもはや難解な対象ではなく、鑑賞者自身の成熟を問い返す場として立ち現れてくるのである。