生きるということー日高正法「啓示」
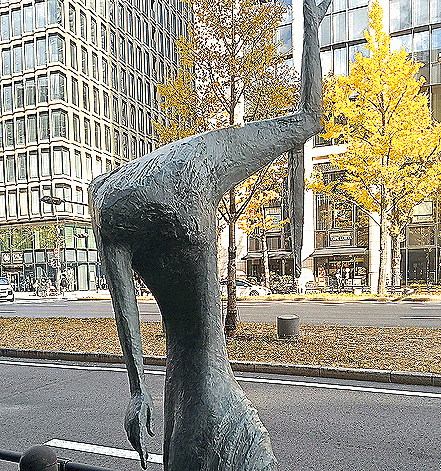
1 街路に立つ問い
大阪・御堂筋の彫刻ストリートには、多くの具象彫刻が並んでいる。人の姿をかたどり、都市の風景に静かな秩序を与える像が多い。その流れの中で、日高正法の「啓示」は、どこか居心地の悪い沈黙をまとって立っている。
左手は天へ、右手は地へ。両腕は地面に対して垂直で、しかも強い緊張を保っている。だが、頭部はない。人の像でありながら、人を説明する要素が欠けている。出会った瞬間、「美しい」とも「分かる」とも言えず、ただ足が止まる。これは像というより、問いが立っているのではないか。そんな感覚を覚える。
その身振りから、誕生仏、唯我独尊の釈迦像が思い浮かぶ。しかし似ているのは、形の輪郭だけである。信仰を支えるための物語も、象徴も、ここにはない。似ているが、帰属先がまったく異なる。その差異こそが、この像の出発点である。
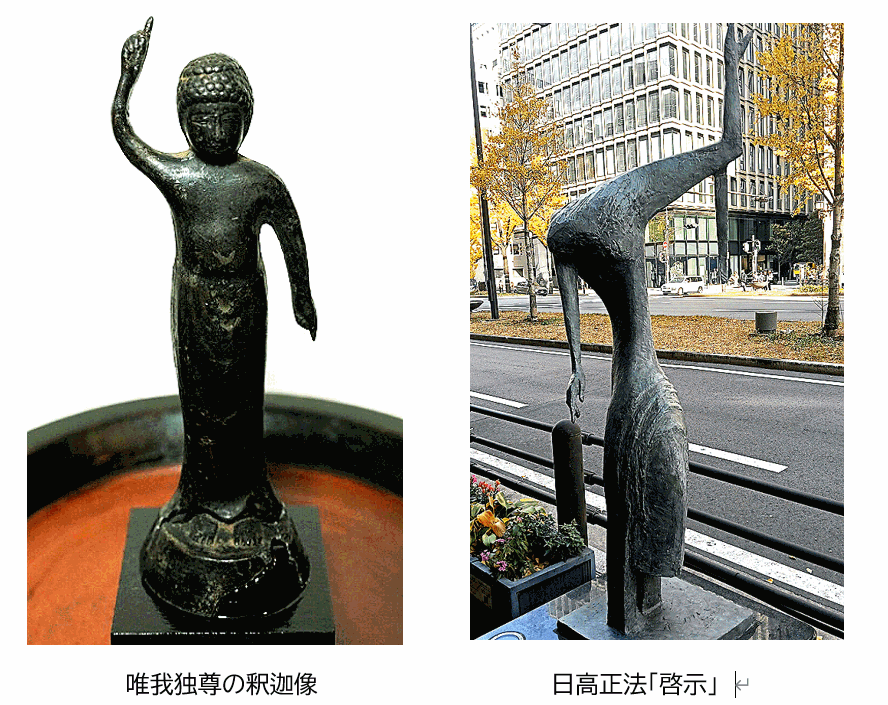
2 啓示という言葉の空洞
「啓示」とは、本来、神が人に真理を示す出来事である。そこには必ず与え手があり、啓示は人間の外部からやってくる。だが、日高正法の「啓示」には、与え手が存在しない。神も仏も、真理の内容も示されない。啓示であるはずなのに、何が啓示されたのかが語られない。
この空白は欠落ではない。意図的な空洞である。日高は、「啓示」という言葉を宗教から切り離し、人間の内部へと移し替えている。ここで起きているのは、真理の授与ではなく、人が自分自身に対して開かれてしまう瞬間である。逃げることも、取り消すこともできない気づき。その出来事に、あえて「啓示」という名を与えている。
3 両腕の垂直――確かに起こったこと
「啓示」の両腕は、ためらいなく垂直に立ち上がっている。これは祈りの姿勢ではない。祈りには願いがあり、依存がある。しかしこの腕は、何かを求めて伸ばされているのではなく、すでに成立した事実を支える軸として存在している。
ここには「これから分かる」のではなく、「分かってしまった」という時間がある。啓示は予感ではない。可能性でもない。それは、すでに起こってしまった出来事であり、その後戻りできなさが、この腕の緊張に刻まれている。
4 頭部の不在――信仰を拒む造形
この像に頭部がないことは、決定的である。宗教像において、頭部は意味の中心であり、悟りや慈悲、神的知性が宿る場所だ。しかし「啓示」は、それを持たない。
これは思考の否定ではない。信仰の否定でもない。むしろ、啓示を理解や信仰の問題に矮小化することへの拒否である。日高が示しているのは、「分かった人」ではなく、分かってしまった後の身体だ。覚醒は理念ではなく、姿勢として現れる。その徹底が、無頭像という選択に表れている。
5 傾く胴体――救済されない世界
両腕が垂直であるのに対し、胴体は傾いている。像は安定して立っているが、どこか世界と噛み合っていない。この傾きは、失敗でも偶然でもない。
啓示があっても、世界は救済されない。気づいたからといって、生活が楽になるわけでも、社会が整うわけでもない。むしろ、気づいてしまったがゆえに、世界の歪みや矛盾が、より鮮明に立ち現れてしまう。
胴体の傾きは、その感覚を引き受けている。「啓示」は、救済の像ではない。救済されないまま立ち続ける人間の像である。
6 語られない脚――地面から逃げないこと
脚は具体的に表されていない。しかし像は、確かに両足で立っている。ここには、超越も離脱もない。啓示は起こったが、人はこの地面から離れない。生活は続き、問題は残る。
脚が語られないのは、現実があまりにも個別で、言葉にしきれないからだろう。だが、立っているという事実だけは消されていない。それは、人間が生を引き受ける最低限の条件である。
7 一体化された人間
「啓示」において、啓示は両腕として立ち上がり、現実とのずれは胴体に刻まれ、生活への立脚は脚として沈黙している。
これらは分断されていない。人間とは、気づきを得ながら、矛盾を抱え、なお現実に立ち続ける存在である。日高正法は、その厄介で、しかし誠実な姿を、物語も救済も与えず、ただ形として差し出した。
「啓示」は答えを与えない。それは、生きるという状態そのものを、問いとして立たせる彫刻である。だからこそこの像は、都市の中で、今も静かに問い続けている。
あなたは、気づいてしまったあと、どのように立ち続けるのか、と。