橋本平八 石に就(つい)てー仙を表現するもの
橋本平八における自然と時間と無意識
Ⅰ.はじめに
彫刻家・橋本平八(1897–1935)は、わずか38年の生涯の中で、日本近代彫刻史において特異な位置を占めた人物である。
彼の代表作「石に就いて」(1928)は、単なる素材研究や造形実験を超えて、自然と時間の本質に迫る哲学的作品として位置づけられると考えられる。 西洋の彫刻が人間の意志や精神の表現を目的として発展してきたのに対し、橋本はこの「石に就いて」でその逆を歩んだ。
写真で見ると、一見何であるか判然としない形がそこにある。
タイトルに「石に就いて」とあるため、私たちは自然と「石だろう」と思う。
だが、作品を前にして私は戸惑った。――これは木で彫られた石なのだ。 なぜ橋本は、木を素材にして「石」を作ったのか。
単なる模刻とも思えない。そこには、何かを「表現したい理由」が必ずあると感じた。
私はこの問いから、橋本が「石に就いて」を通して何を創造しようとしたのか、その本質を探りたいと考えた。 本稿では、その探究のために次の三つの視点から考察を試みる。
①「観る」から「聴く」へ ― 石の声を聴くとは
②無意識的創造 ― 「聴く」ことで形が生まれる
③橋本が到達した仙の思想 ― 自然と一体化する存在哲学 この三つの視点から考察(妄想?)することにした。
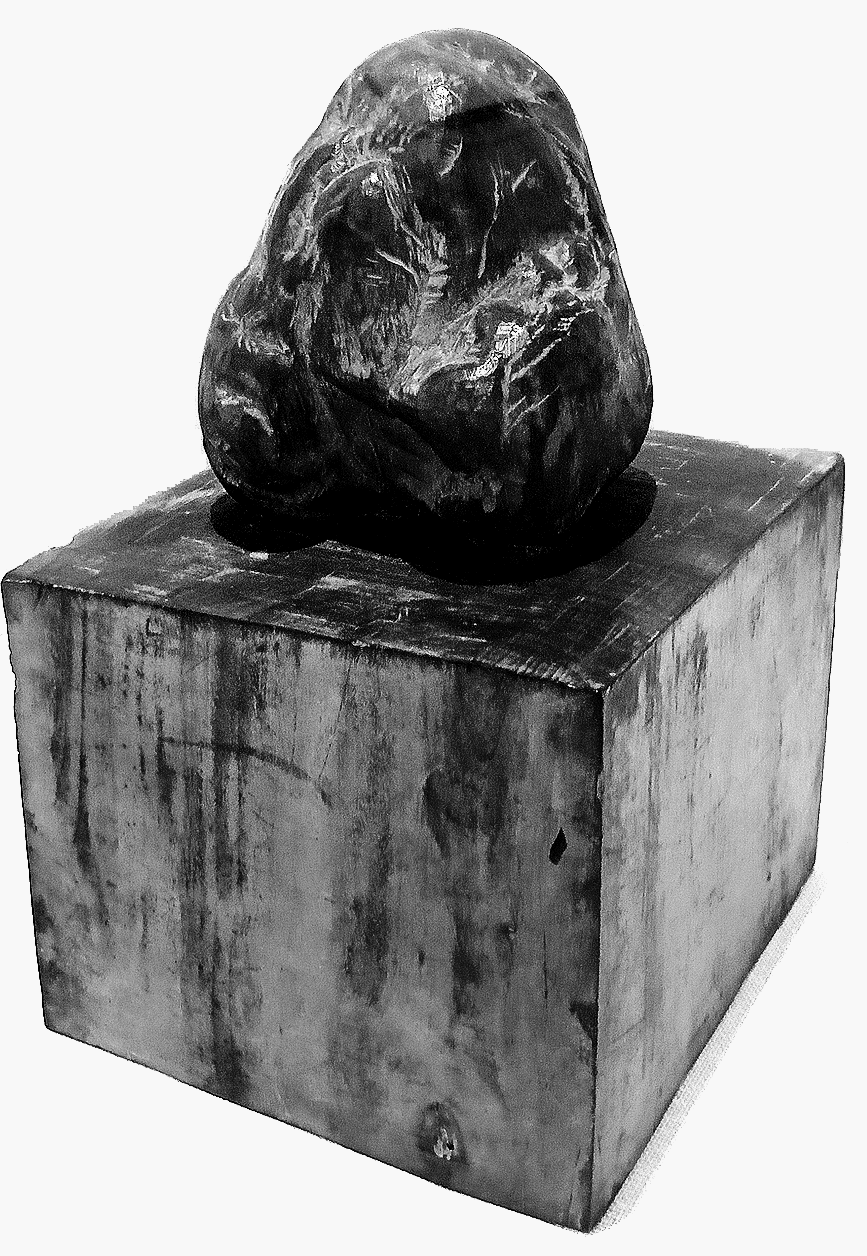
Ⅱ.「時間の容れ物」としての石、その声を聴くとは
橋本の「石に就いて」は、単なる素材の探究ではなく、「観る」芸術から「聴く」芸術への転換を示す作品である。 石という素材を、橋本は単なる物質としてではなく、自然が長大な時間をかけて創り上げた生命的存在として捉えていたと考えられる。
彼が彫刻に求めたのは、形の新奇性ではなく、自然の中に眠る時間の記憶を、石を通して可視化することであった。 橋本の制作態度は、「石は死物にして生物なり」と彼自身が記したように、石から静かな時間の呼吸、すなわち石が自然の中で形を得る過程を「聴く」ことにあった。
橋本は石を通してその長大な時間の呼吸に耳を傾け、素材の声を聴き取り、わずかに手を加えた。それこそが橋本の制作の本質である。
彼の創造とは、単に「形をつくる」ことではなく、「形が生まれるのを聴く」ことであったといえよう。 「聴く」という態度の源流は、東洋的な感性にある。
宋の詩人・蘇軾は「暫來石上聴松声(しばらく石上に来たりて松声を聴く)」と詠んでいる。
私たち現代人は「観る」という認知に偏りがちであるが、東洋には「聴く」という別の認知の方法が存在する。
蘇軾の自然観は、「観る」よりもむしろ「聴く」という姿勢に貫かれており、それは対象を外から観察・把握するのではなく、自然の声に耳を傾け、心を通わせるという、東洋特有の感受の仕方である。 西洋の美学においては、「観る(to see)」が芸術の基本的態度とされ、見る主体と見られる客体が分離し、視覚によって世界を構築する立場が支配的であった。
これに対し、東洋の詩や絵画、書、思想では、「聴く(to listen)」が中心的な認識行為である。
聴くとは、能動的に支配するのではなく、自然の側から語りかけてくるものを受け入れる行為である。
そこには主体と客体の分離がなく、むしろ両者の呼吸の一致がある。蘇軾が描いた世界はまさにこの「聴く世界」であった。彼は自然を観察するのではなく、自然と対話し、共に生きた。
その姿勢こそが、自然とともに生きる時間のとらえ方である。 橋本の彫刻もまた、「時間を刻むもの」から「時間を宿すもの」へと変化した。
彼の作品は、自然の長い生成の過程をそのまま抱え込んだ石、すなわち悠久の「時間の容れ物」としての石を表現している。
このことが橋本作品の本質であったといえる。 このような考え方は、直線的・進歩的な西洋的時間観とは異なり、東洋的な「沈殿し、循環する時間」の感覚に呼応している。
石という存在そのものが時間とともに呼吸し、過去・現在・未来が溶け合うという世界観である。 同様の東洋的認知の仕方は、龍安寺の石庭にも見出される。
庭に置かれた石を「観る」と同時に「聴く」ことで、時間の流れや沈黙、風の音を感じ取ることができる。
それは古来、日本人が育んできた、自然と自己の世界を「共鳴」として捉える聴く美学にほかならない。
石庭の作者の意図も、単に庭を目で見ることだけでなく、時間・風・沈黙・自己の呼吸を「聴く」ことにあったと考えられる。 同じように、橋本にとって石とは、ただの物質ではなく、自然の声を発する存在であった。
その声を聴き取り、最小限の手を加えることで、素材の内に沈殿した時間と生命を呼び覚ます――それが彼の創造の根幹である。 《石に就いて》から自然が発する声を聴くとき、鑑賞者自身もまた、その「聴く」体験に参与する。
この作品は、鑑賞者に「聴く」という感覚を促す装置であり、その存在は単なる視覚的対象を超えている。
橋本の石は、自然の声を媒介し、人間が時間とともに呼吸することを思い出させる装置である。
そこにこそ、この作品の存在価値がある。
Ⅲ.無意識的創造 ― 「聴く」ことで形が生まれる
橋本平八の創造におけるもう一つの重要な特徴は、無意識の働きである。
彼の作品には、意識的構成や理性的操作の痕跡がほとんど見られない。
むしろ、素材そのものの性質に導かれて形が立ち上がるような、自発的生成のプロセスがある。 この態度は、カール・ユングの言う「集合的無意識」にも通じる。すなわち、個人の内面を超えて、自然と人間が共有する根源的な生命意識の層にアクセスする創造である。
橋本は、自然を「外にある対象」とは見なさず、自らの内に同居する存在として感じ取った。
この「聴く創造」は、西洋のロダンやブランクーシのように、意識によって形を構築する芸術とは正反対である。 西洋が「人間の意志による造形」を目指すのに対し、橋本は「自然が人間を通して形を生む」ことを志向した。
それは、意識ではなく無意識の層において自然と共鳴する、非主体的でありながら深く人間的な創造であった。
彼にとって、創造とは自己を主張することではなく、自然の力が自らを通して形を現す瞬間に身を委ねることであった。 私はこの橋本の創造態度を思うとき、長谷川等伯の「松林図屏風」を思い出す。この作品にもまた、橋本の「聴く創造」と同質の無意識的呼吸が流れている。
等伯が描いたのは、単なる松の風景ではない。霧に包まれ、姿を曖昧にした松の立ち姿は、描かれた形であるよりも、むしろ自然の気配そのものである。
そこには構図の計算も技巧の誇示もない。墨の濃淡と余白が互いに呼応し、画面の内と外の境界が静かに溶けてゆく。
その筆は、意識が描いたのではなく、自然が等伯の手を通して形を現しているかのようである。 橋本が石の声を聴きながら形を浮かび上がらせたように、等伯もまた、霧の奥に潜む松の声を聴いていたのだろう。
両者に共通するのは、創造の出発点を「意識の操作」ではなく、「無意識の共鳴」に置いている点である。
無意識の創造とは、理性の放棄ではなく、自我の力を一度沈めて自然のリズムと一体化することである。
そのとき、創造者は主体として自然を支配するのではなく、自然の側から立ち上がる形の媒介者となる。橋本の石が「時間の呼吸」を宿すように、等伯の松もまた「自然の呼吸」を可視化している。 両者の作品に共通して流れるのは、深い沈黙である。しかしその沈黙は空虚ではない。そこには、自然と人間のあいだに流れる見えない対話の響きが満ちている。
それは音なき「聴く空間」であり、意識の言葉を超えた場所で形が生まれてくる。この「沈黙の空間」こそ、無意識的創造が開かれる場所であり、人間の創造が自然の生成と重なり合う臨界点である。 両者の芸術におけるもう一つの共通点として、死の体験がある。
長谷川等伯は、最愛の息子・久蔵の死を契機に、「松林図屏風」を描いたと伝えられている。
一方、橋本平八もまた、母の死を通して、生命の根源や永遠性に向き合うようになった。
いずれも、個人的な悲嘆を超え、生と死の循環に触れる契機として死を受け止めている。 等伯の「松林図屏風」は、静謐でありながら、深い哀しみが漂う。墨の濃淡に溶ける松の姿は、生と死、存在と非存在のあわいに揺らめくようである。筆の痕跡はほとんど消え、霧の中に溶けるようなその姿は、まるで死の彼方から立ち上がる記憶の残響である。
そこにあるのは、個人の悲嘆を超え、自然そのものの呼吸と一体化した永遠の静けさである。 橋本の「石に就いて」もまた、死の静けさを内に宿している。彼が石に刻んだのは、生命の表層的な動きではなく、死を通して見出される永遠の生命であった。
母の死を経験した橋本にとって、死は断絶ではなく、時間の中に溶け込み、循環する生命の現象であったのだろう。石は、静止しているように見えて、長大な時間の流れとともに呼吸している。
それは、死を受け入れた先に現れる生命の深い呼吸そのものである。 このように見ていくと、橋本と等伯の芸術は、死を悲劇としてではなく、存在の深みに降りる契機としての死を通して成熟している。
死は、彼らにとって創造を終わらせるものではなく、むしろ創造を深化させる転換点であった。死の体験によって、彼らは“個人の意識”という枠を超え、無意識の領域に流れる自然のリズムと接続することができた。
そのとき、創造は「自分がつくる」行為ではなく、世界が自らを通して形を得る現象へと変化した。 この転換は、芸術家としての成熟を超えて、存在そのものの変容である。死の体験を経て、彼らは「生の反対としての死」ではなく、「生命の循環の一部としての死」を感じ取った。
その感受の深さこそが、「松林図屏風」と「石に就いて」に通底する静謐な気配を生み出している。 言い換えれば、両者の作品は「死から生まれた芸術」である。それは悲しみの表現ではなく、死を通して開かれた生命の永遠性の表現である。
死は終わりではなく、自然の時間に沈殿し、再び形として現れる契機であった。
橋本と等伯は、その沈黙の中に、死と生の呼吸が溶け合う「無意識の宇宙」を観ていたのである。 こうして見ると、橋本平八と長谷川等伯は、時代も技法も異なりながら、ともに「意識の芸術」から「無意識の創造」へと至った点で深く通じ合っている。彼らの芸術においては、創造とはもはや人間の営為ではなく、自然そのものの生成の延長であった。
この地点において、芸術は宗教にも似た静謐を帯び、創造者は「自然とともにある存在」へと変容してゆく。 彼らが最終的に到達した境地―それはもはや人間の創造ではなく、自然の呼吸を媒介する“仙的創造”の世界であった。
この無意識的創造の果てに、橋本平八は、人間と自然の境界を超え、存在そのものとともに生きる芸術へと歩みを進めていったのである。
Ⅳ.橋本が到達した仙の思想 ― 自然と一体化する存在哲学
橋本の創造をさらに深く理解するためには、東洋思想の「仙」という概念が鍵となる。「仙」とは、「人」と「山」から成る文字で、もともと「山に住む人」を意味した
後に、「自然と調和し、俗世を離れた理想的存在」として理解されるようになり、その思想的基盤は老荘思想の「無為自然」にある。
老子は「道法自然」と述べ、あらゆる存在は自然の法に従うべきだと説いた。
荘子は「真人」「至人」という概念を通して、天地とともに生きる人間の理想像を描いた。 この「仙」の精神とは、自然を超越するのではなく、自然とともに呼吸し、その無限のリズムの中に生きる人間の在り方である。 橋本の創造は、まさにこの「仙的精神」の現代的表現といえる。彼は自然を征服するのではなく、自然の流れに身を委ね、素材の中に宿る「気」や「時間」の声に従って作品を生み出した。
橋本の彫刻における創造とは、人間の意志による形の支配ではなく、自然が自らの法にしたがって形を顕す場を整える行為であった。その意味で橋本は、「自然の中に棲む芸術家」であり、彼の彫刻は「自然とともに呼吸する芸術」である。 老荘思想における「無為」とは、何もしないことではなく、不自然を為さないという意味である。人間の意識や欲が自然の流れを乱さないとき、自然の生命はもっとも純粋な形で現れる。
橋本が石の声を聴き、最小限の手を加えたのは、この「無為の創造」である。そこには、自然に身を委ねながらも、素材が訴える声に最も敏感に反応する繊細な感受性がある。
この態度こそ、東洋的な意味での「仙の境地」であり、人為を脱した創造であった。 しかし、橋本の仙的創造は、単に老荘的な自然回帰ではない。
そこには、日本的な生命観――生も死も同じ流れの中にあるという無常の感覚が深く息づいている。
彼にとって生命とは、誕生と消滅を繰り返す時間の流れの中で、絶えず形を変えながら存在し続けるものだった。
「石に就いて」における「石」は、時間の沈殿であると同時に、生成と崩壊を内包した存在である。
その姿は、永遠の中に生と死が交錯する日本的生命観―「いのちは流れであり、形はその一瞬の息づかいにすぎない」という感覚に結びついている。 この生命観は、仏教的無常観と神道的自然観の交錯する場所にある。
橋本は、自然を「対象」として彫るのではなく、自然そのものの中で「生きる」ことで形を生じさせた。それは「聴く」という受容的創造態度と、「無意識的共鳴」によって可能となる。 つまり、橋本の創造とは、自然の呼吸とともに存在すること自体が芸術であるという境地に至っている。 「仙」とは、超越者ではなく、自然の法とともに生きる人である。
そして、橋本の彫刻における「仙」は、山中にこもる隠者ではなく、時間の中に棲む者である。
石を通して時間とともに生き、生成と風化のあいだに自己を溶かし込むその在り方は、まさに「現代の仙」と呼ぶにふさわしい。
彼の作品は、形の美を超えて、存在の呼吸そのものを刻む芸術である。
そこでは、芸術はもはや人間の表現ではなく、自然そのものの現れであり、橋本自身が自然の一部として呼吸する「存在の芸術」へと昇華している。 この境地において、橋本の創造は老荘の「無為自然」と日本的な「無常の美」を融合させた、東洋精神の完成形であったといえよう。
それは、「自然を聴き、自然とともに生きること」こそが、芸術の究極の姿であるという、橋本の静かな信念の表現である。
V. 結語 ― 聴くことから存在へ
橋本平八の芸術は、近代彫刻の文脈を越えて、人間と自然の関係そのものを問い直す行為であった。彼は「形をつくる」ことを目的とせず、形が生まれる瞬間を「聴く」ことに生の意味を見いだした。
その態度は、意識による造形から、無意識による共鳴へと転じ、やがて自然とともに存在する「仙の境地」へと至った。 「聴く」とは、外界の音を受け取ることではない。それは、自然の奥に流れる時間の声を聴くことであり、世界の生成の中に自己を溶かす行為である。このとき、芸術とはもはや人間の表現ではなく、自然が自らを語るための媒介となる。橋本の作品が放つ静謐な気配は、そのような「自然の呼吸」が形となった証しである。 彼の彫刻において、石は単なる物質ではない。それは、悠久の時間を沈殿させた「生命の容れ物」であり、生と死、生成と風化を繰り返す自然の呼吸の具現であった。橋本は、その呼吸を「聴き」、そこに最小限の手を添えることで、人間と自然のあいだに新たな関係を見いだした。 彼が到達した「仙的創造」とは、自然に帰ることではなく、自然とともに生きる意識の到達点である。
それは、無為にして自在、沈黙の中で世界とともに呼吸する存在のあり方であり、「自然の中に棲む芸術」そのものである。橋本の彫刻は、物質を超えた「時間の詩」であり、人間が世界とともに在ることの証言として、静かに立ち続けている。 この橋本の芸術精神は、孤立したものではない。
それは、日本の美の根底に流れる「自然との共鳴」の系譜に位置づけられる。
龍安寺の石庭における沈黙の構成も、長谷川等伯の「松林図屏風」における余白の呼吸も、いずれも自然の声を「聴く」ことで形が生まれる芸術である。
橋本の「石に就いて」は、この日本的感性の現代的継承であり、「自然とともにあること」こそが創造の根源であるという思想を、彫刻という形で再び顕した。
すなわち、橋本の追及した芸術は、古代から連綿と続く日本芸術の生命観の延長線上にあるといえよう。 いま、私たちはこの「石に就いて」の前に立つとき、それを「観る」のではなく、「聴く」べきなのかもしれない。石の奥に沈む時間の声を、あるいは私たち自身の生命の呼吸を。
そこには、自然と人間、意識と無意識、生と死のすべてが溶け合う、ひとつの世界が広がっている。 橋本の芸術とは、その世界の沈黙を聴くことである。
そしてその沈黙の中に、私たちは再び、生きるとは何かという問いに触れることになる。 以上